下請法のねらい
現在、下請取引の適正化は、政府の最重要課題の一つとなっているといっても過言ではない。岸田政権の経済政策である「新しい資本主義」は、「成長と分配の好循環」をスローガンとして掲げている。このうち「分配」戦略の筆頭柱として挙げられているのが、働く人への分配機能の強化である。これは、企業が、株主だけでなく従業員や取引先にも恩恵を共有する「三方よし」の経営を行うことに導こうとするものである。そして、その手段として、下請取引に対する監督体制を強化するものとされている。
下請取引に対する規制の中核にあるのが下請法(下請代金支払遅延等防止法。昭和31年6月1日法律第120号)である。ただ、下請法が何を保護しようとしているのか、意外とあまり正確には理解されていないように見受けられる。下請法について多くの方が持っているイメージは、「下請事業者を保護する法律である」といったものではないだろうか。これは一面では正しいが、それだけではない。下請法は、その直接の目的として、「親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護」するものと定めている(同法1条)。すなわち、下請取引の公正化こそが、下請法が実現しようとするものである(図表1)。下請事業者を保護する政策手段としては、下請企業の育成・振興を図ることや、下請取引の内容につき積極的に調整に乗り出すことが考えられる。しかし、下請法は、こうした産業政策的な手段によるのではなく、取引を公正化することを通じて下請事業者を保護しようとするものであるといえる。こうしたことから、下請法は、独占禁止法の補完法として位置付けられている。
図表1 下請法のねらい
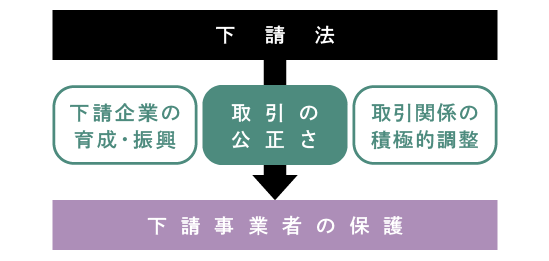
それでは、取引が「公正」であるかどうかは、どのように判断されるのであろうか。これは下請法の根幹の理解に関わるものであるが、明確な答えを出すことは容易ではない。
下請法において「公正」ではないと判断される行為は、二つのタイプに類型化することができる。一つは、当事者間でいったん設定した取引条件を一方当事者(親事業者)が事後的に変更することである。これにより、他方当事者(下請事業者)は予測できない不利益を被ることとなってしまいがちである。そして、「公正」ではないと判断される類型の二つ目は、そもそも当事者間で設定された取引の条件自体が不合理であるという場合である。以下、この二つの類型について概観してみよう。
予測できない不利益を及ぼす行為の規制
まず、いったん設定された取引条件を変更することが「公正」ではないと評価される類型である。具体的には、支払遅延、代金の減額、返品、発注の取消し(受領拒否)といった行為が当てはまる。こうした行為によって相手方(下請事業者)が不利益を受けることは比較的明確であり、たとえ外形上は下請事業者の「同意」があるとしても、それは真の意思に基づくものではないことが多いであろう。
もちろん、相手方が発注後の取引条件の変更につき真に同意しているケースもある。しかし、個別の事案ごとに相手方の「同意」が真の意思に基づくものであるかどうかを判断していては、下請事業者の保護は十分に図れないこととなってしまう。そこで下請法では、下請取引の公正化による下請事業者の保護を簡易迅速に図るため、発注後に取引条件を変更する行為は、実際に下請事業者が真に同意しているか否かを問わず、下請事業者の責めに帰すべき理由がない限り、違反行為とみなされる。
このような取引条件を反故にする行為は、いわば古典的な下請法違反類型である。これらに違反した親事業者には、勧告がなされて公表されるといった厳しい行政上の措置が講じられてきた。とりわけ、「“同意”があってもダメ」というのは、取引現場での「常識」とは異なるものであり、意図せずして下請法違反を招く原因となっている。
現在でも、依然としてこうした違反は跡を絶たない状況にあり、企業として最も注意すべき基本的な下請法違反類型であるといえる。
不合理な取引条件の規制
取引条件の不当性の判断枠組み
次に、不合理な取引条件を設定すること自体が「公正」ではないと評価される類型である。発注する物品の対価を著しく低く設定すること(買いたたき)がその典型である。本来の取引の条件ではないとしても、取引に付随して相手方に経済上の負担をかけること(経済上の利益の提供要請)や、本来の取引に付随して別の不要な商品を購入させること(購入・利用強制)も、そのような行為自体の不合理性が問われるものである。
このように相手方に不利益となる取引や行為は、それが明らかに経済合理性を欠くものであるならば、「公正」ではないものとして違法と評価されやすくなる。しかし、取引や行為自体の不合理性を判断することは容易ではない。対価の設定についてみれば、対価はコストの積み上げだけで決まるものではなく、どのような対価であれば経済合理性があり、どのような対価であれば合理性を欠くものであるのか、一義的に判断することは困難である。
そのため、取引条件の「公正」さの判断においては、取引条件そのものの合理性だけでなく、別の要素も考慮されることとなる。それは、「当該取引の条件を定めるにあたって、当事者間で十分に協議を経ているか」ということである。当事者双方が十分な協議を経て設定された取引条件であるならば、その内容は合理的なものであると通常は見込まれるからである。
もちろん、協議の場を設ければそれで問題がなくなるというわけではない。取引条件の不合理性が明確な場合には、単に協議の場を設けたというだけで正当化されるものではない。他方、対価の設定のように、それ自体の経済合理性の判断が容易ではない場合、当事者間で十分協議を行って対価を定めたものであるならば、当該対価設定は合理的なものとして適法と判断されやすくなる。
このように、取引条件の設定自体が下請法に反するかどうかは、条件自体の合理性と、当事者間で十分に協議したかというプロセスの両面を相関関係的に評価して判断されるものである。
取引条件の規制手法
このように、取引条件を公正なものとするためには、当事者間で十分な協議がなされることが重要であり、当事者の自主的な対応によるところが大きい。そのため、取引条件に関する下請法の運用においても、「当事者が自主的に適正な取引を行うよう促す」という手法が主として用いられるようになっている。
すなわち、経済産業省(中小企業庁)は、下請中小企業振興法に基づき、下請事業者との適切な取引関係を構築するために親事業者に求められる事項を「振興基準」として定めている。これは、下請取引におけるベストプラクティスを示すものである。また、経済産業省(中小企業庁)は、業種別に下請取引適正化推進ガイドラインを定めている注1。
その上で、経済産業省(中小企業庁)は、2016年以降、下請取引の関係各業種の団体に対して、サプライチェーン全体での取引適正化と付加価値向上に向けた自主行動計画の策定と実行を要請している注2。これは、親事業者側が下請取引の適正化に向けて主体的に取り組むことを促すものである。
さらに、2020年以降、内閣府と経済産業省(中小企業庁)は、個々の親事業者自身が「パートナーシップ構築宣言」を自主的に行う枠組みを設けている。これは、振興基準の遵守等を内容とする宜言を行った事業者は、指定のロゴマークを使用することができるほか、政府補助金の優先採択の対象とすることにより、個々の事業者による取引適正化への自主的な取組を促進しようとするものである注3。
このような事業者団体や事業者自身による自主的な措置を促す政策は、下請法の法制上の建付けに適ったものである。すなわち、下請法では、公正取引委員会によって勧告がなされる場合であっても、それはあくまで行政指導であって、強制力のあるものではなく、対象事業者がそれに応じて自主的に措置を講じることを前提にエンフォースメントが成り立っている。当事者の自主性に委ねた法制度であるからこそ、サプライチェーン全体の生産性向上等、大企業と中小企業が共に成長できる持続可能な関係を構築するという積極的な競争政策が可能となる。これが近年の下請法を含む取引適正化政策のメインストリームになりつつあるといえる。
条件改定の合理性
話を戻そう。取引条件の設定自体が不合理であると判断されるのは、具体的にどのような場合なのだろうか。
対価の設定についていえば、ある物品の単価を1,000円とする場合、「なぜ1,000円なのか?」を客観的に説明することは容易ではない。そのため、単価1,000円が安すぎるのかどうかを判断することは通常は困難である。しかし、従前は単価1,000円であった物品について、今後は単価900円に改定する場合、「なぜ100円分の単価引下げを行うのか?」については、本来、それなりに合理的な説明ができるはずである。すなわち、取引の条件を従前のものから改定しようとする場合には、改定を求める側においてその説明責任を果たすことが通常は可能であり、それが求められる(図表2)。
図表2 価格の変更
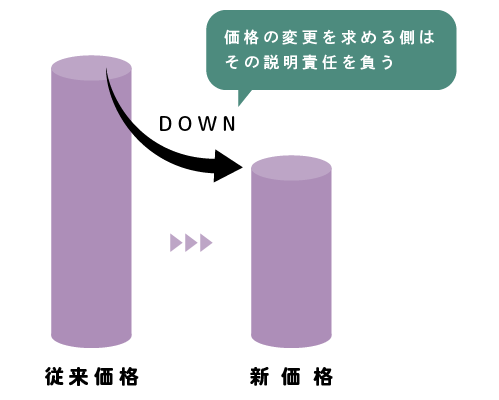
たとえば、新年度から製品の単価を従前よりも3%引き下げて発注しようとする場合、たとえこれまで年3%ずつ単価を引き下げてきたからといって、今年も3%の単価引下げが合理的なものといえるわけではない。
単価の引下げは、下請事業者においてコストダウンが生じており、親事業者においてそれに相応の貢献をしたものであることを前提とするものである。単価の引下げ改定を求める親事業者としては、親事業者の寄与度に応じた単価への反映である旨を下請事業者に説明したうえで、下請事業者側の貢献も十分に勘案し、新単価を定めることが求められる。
他方、対価を据え置くことが「買いたたき」として下請法上問題となることもある。近年、下請事業者のコストが上昇傾向にある。最低賃金の引上げにより労務費が上昇し、原料やエネルギーコストの値上げも相次いでいる。こうしたコスト上昇につき、下請事業者側に帰責性はない。このような場合において、下請事業者側がコスト上昇を理由にその合理的根拠を示して対価の値上げを要請したにもかかわらず、親事業者が協議に応じることなくこれを無視し、発注単価を据え置くことは、買いたたきに該当すると判断されることがある。
支払条件の合理性
ほかにも、取引条件の設定につき下請法上問題となる場面は、多数ある。最近では、型保管等の適正化や、知的財産の譲渡等の適正化などがクローズアップされている。その中でも喫緊の課題として注目を集めているのが、手形を支払手段とする場合の取扱いである。
下請法では、支払条件の設定につき過度に下請事業者に不利益とならないようにするため、支払期日規制が設けられている。すなわち、親事業者は、下請取引の対象となる給付を受領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内において支払期日を定めなければならないものとされている(2条の2)。なお、ここでの「支払い」は、現金にて行うのが原則である。
親事業者が支払期日において手形を振り出した場合、下請事業者が手形金の支払いを受けるのは支払期日よりも先の手形の満期日であり、上記の支払期日規制が潜脱されるようにも思われる。しかし、手形は、下請法制定当時から商慣習として広く利用されていた。手形の満期日をもって「支払い」を受けたものとして上記の支払期日規制を適用することは、実務上大きな混乱を招くことが懸念される。そのため、「支払期日において振り出された手形は即日に割引等により現金化することが可能である」というロジックにより、下請法上も手形払いは支払期日規制に抵触しないものとして、これまで許容されてきた。
もっとも、手形の振出日から満期日までの期間(手形サイト)が長期にわたる場合には、たとえ割引による現金化が可能であるとしても、高額の割引料を要することとなり、下請事業者の利益を不当に害することが多くなる。現金に代わる支払手段を用いるのは、基本的には親事業者側の都合であるにもかかわらず、当該支払手段に要するコストを下請事業者に負担させることは不合理であると判断されやすい。そのため、下請法では、割引が困難な手形を交付すること自体が規制対象とされている(4条2項2号)。どのような場合に割引が困難な手形を交付するものと判断されるかについては、現在のところ、手形サイトが4か月(繊維業については3か月)以上のものであることが基準とされている注4。
そうしたところ、2021年3月、公正取引委員会と中小企業庁は、下請代金の支払いに係る手形(電子記録債権も同様)のサイトは、おおむね3年以内(2024年まで)をめどに、60日以内とするよう要請がなされた(図表3)注5。また、同時に、手形等の割引料負担に関する協議を促進するため、手形等により下請代金を支払う場合には、本体価格とは別に割引料等のコストを示してこれを勘案した下請代金の額を定めることも要請されている。これは、手形払等によるコスト負担を下請事業者にしわ寄せすることの懸念が再認識されるようになり、下請取引のさらなる適正化を図ろうとするものである。
図表3 手形サイトの短縮化等に関する要請
|
「下請代金の支払手段について」(公取委・中企庁2021年3月31日要請) |
|
手形は、かつてはサプライチェーン全体で資金繰りの負担を分かち合うという機能を有していたが、現代では、資金調達の手段が多様化し、手形の役割が低下している。現に、政府は、2021年6月、2026年をもって手形の利用を廃止するという方針を閣議決定するに至っている注6。
下請取引に携わる企業としては、まずは2024年までに支払いの現金化を進めるとともに、手形払い等を継続する場合であっても、手形サイトを60日以内に短縮することが求められている。これは、親事業者の資金繰りに直結する問題であるとともに、サプライチェーン全体で取り組まなければならない問題である。「3年」という期間は、そのための準備期間として決して長いものではないであろう。
むすびに代えて
産業構造の大きな転換期にある今、企業にとって外部との協働によるオープンイノベーションが欠かせなくなっている。サプライチェーンにおいても、上下関係で階層的に分断するのではなく、サプライチェーン全体で叡智を結集して活用することが求められている。
ただ、そのためには、取引先において自由な発想を生み出す環境を整えることが必要となる。合理的な取引条件を設定し、また、いったん設定した取引条件を反故にしないことは、当たり前のことではあるが、イノベーションを生み出す大前提として重要な一歩となるものであろう。
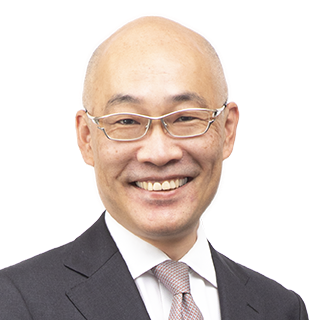
長澤 哲也
弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
1994年東京大学法学部卒業。1996年弁護士登録。2001年University of Pennsylvania Law School卒業(LL.M)、同年~2002年Morgan, Lewis & Bockius, Washington, D.C.勤務(独禁法セクション)。2002年ニューヨーク州弁護士登録。独禁法、下請法、景品表示法等の競争法分野を中心に、当局調査対応や訴訟を数多く手がけるほか、国内外の企業の競争戦略実現に向けた積極的アドバイスを得意とする。2016年~神戸大学大学院法学研究科客員教授。主な著作として、『独禁法務の実践知』(有斐閣、2020年)、『優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第4版〕』(商事法務、2021年〔初版2011年〕)。

