はじめに(再掲)
2021年4月21日、参議院で「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が可決成立し、4月28日に公布された。
これらの法律(以下「改正法」という)は、「所有者不明土地問題の解消」をテーマに行われた法制審議会民法・不動産登記法部会(以下「法制審部会」「部会」と略すことがある)での約2年にわたる議論を踏まえてできあがったものであり、不動産登記にかかる手続法レベルの改正にとどまらず、長らく抜本的な改正がされていなかった民法の物権法分野の規定にも大きな変更を加える内容となっている。
しかし、それだけ大きな改正でありながら、この法案に関する報道等が、「相続登記の義務化」や、(法人が対象から外れた)「土地所有権の国庫帰属制度」といった市民向けのテーマに偏ってなされがちなこともあり、企業実務に携わる方々からは、「自分たちの仕事にどう影響するのかピンとこない」という話も聞くところである。
そこで、本記事では、今般の改正法の多岐にわたる内容のうち、特に企業実務に影響するポイントに絞って、改正法の概要と今後の実務に与える影響について2回に分けて概説する注1。
第2回は、主に図表1のBに示す今改正の2本目の柱である「所有者不明土地の発生を予防する方策」(不動産登記法改正等)を取り上げる。※第1回はこちら
図表1 所有者不明土地問題の解消に向けた二つのアプローチ(再掲)
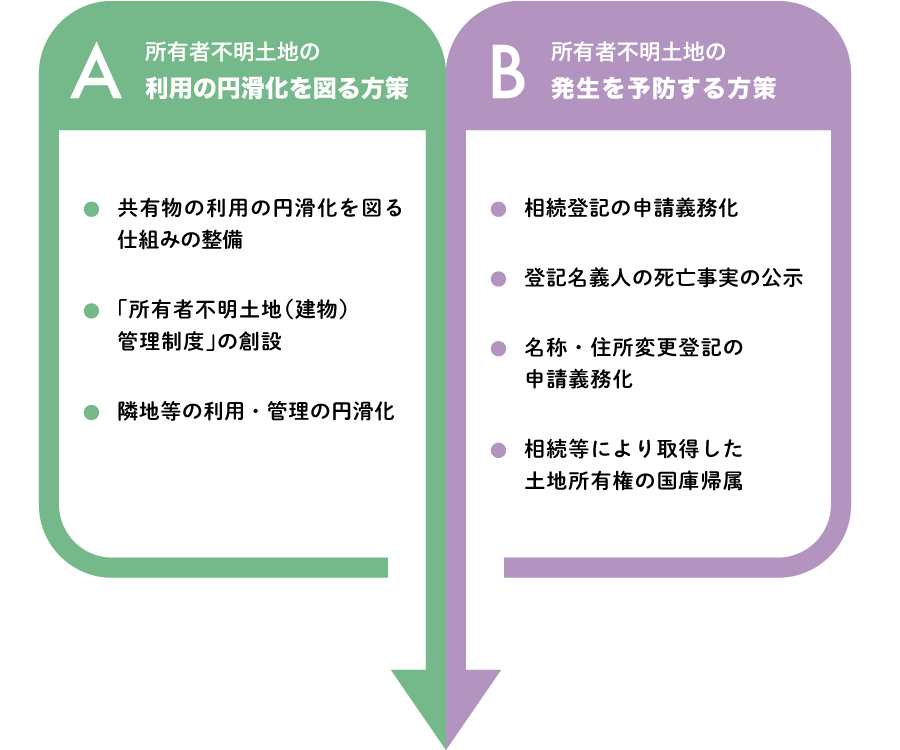
予防的な方策の導入とその生かし方
不動産登記の新たな「公示」機能への期待
さて、「所有者不明土地の発生を予防する方策」については、所有者不明土地発生の最大の原因とされた「相続」登記対策注2に重点が置かれていることもあり、企業実務には直接関係しない事項が多い。
当初は、「土地の所有権を放棄できるか」という大局的な観点から議論されていた「土地所有権の国庫帰属制度」も、政策的な考慮を優先して結果的に「相続等(相続又は相続人に対する遺贈)により所有権の全部又は一部を取得した」土地に対象が絞られることになり(相続土地国庫帰属法2条1項)注3、この制度を施行時点で企業が利用することは困難となっている注4。
ただ、一連の方策により、「登記名義人死亡等の事実が公示されるようになる注5ことで一歩進んだところから所有者探索作業を開始できる」「新設される相続人申告登記制度注6によりアクセス可能な相続人を見つけ出すことが容易になる」といった効果も見込まれるため、各企業の用地取得・管理の実務上、一定の負担軽減につながる可能性は十分にあると思われる。
名称・住所等の変更登記義務化を契機とした自社所有土地登記の再点検
一方、このような予防施策の一環として企業実務にも直接影響するのが、登記名義人の名称(商号)や住所の変更登記を義務付ける規定の創設である(改正不動産登記法76条の5)。
これまで住所変更等の登記をするかどうかはあくまで任意と考えられていたことから、本店の移転等に伴って住所が変わっても、所有するすべての土地の変更登記をすることまではしない(土地の第三者への譲渡等、登記を整えることが必要になったタイミングで対処する)という対応をする会社も多かった。しかし、本改正後は、名称・住所等の変更日から2年以内に変更登記申請をしないと5万円以下の過料(改正不動産登記法164条2項)を科されるリスクが生じることになる。
ただし、この規定は、施行まで約5年の猶予期間が設けられており(改正法附則1条3号)、その間に登録免許税の減免等の負担軽減措置がなされる可能性がある注7。さらに、今回の改正では、会社法人等番号を登記事項に追加した上で(改正不動産登記法73条の2第1項1号)、不動産登記システムと法人・商業登記システムの連携を図り、法人の名称や住所が変更された際に登記官が職権で登記を行えるようにすることも予定されている(改正不動産登記法76条の6)ため注8、新たに創設される所有不動産記録証明制度(改正不動産登記法119条の2)等も活用しつつ、保有するすべての土地に自社の法人等番号を紐付けることで、登記の適正化を円滑に進めるとともに、それ以降の登記事項の変更漏れのリスクを大幅に減らすことも可能となるのではないかと思われる。
コスト削減の大号令のもと、歴史ある大企業ですら自社用地の管理や登記の整備等に十分な人的リソースを割きづらくなっている現状を踏まえれば、これは実に画期的な改正といえるだろう。そして、各企業の実務者としては、今後、改正法施行までの間に公表される具体的な手続や経過措置にかかる運用の詳細等を把握した上で、今回の改正のメリットをフルに生かす方向で「義務化」への対応を図っていくことが望ましいと考える。
おわりに
本記事において2回に分けて紹介した一連の法改正は、令和2年改正土地基本法6条で明記された「土地所有者に土地の利用及び管理等に関する「責務」を課す」という考え方のもと、裁判所や登記官が関与する新たな仕組みとともに、土地所有者自身が自主的にアクションを起こせるようなルールも整えることで不動産の適正な管理と利活用を図ろうとするものといえる。
また、一連の法改正は、これまで「対抗要件」という位置付けのもと、当事者の意思に委ねることが原則とされていた不動産登記のあり方を大きく変える可能性を秘めたものでもある注9。
改正事項の多くは現時点で施行日未定であり注10、今後公表される運用面の施策によっても実務への影響の度合いやとるべき対応は変わりうるが、企業内実務のバックグラウンドに支えられながら改正要綱の審議過程の末席に身を置いていた者としては、各企業の実務の現場が一連の法改正のメリットを存分に生かせるようになることを願ってやまない。
注1 筆者は法制審議会民法・不動産登記法部会の委員として一連の法改正にかかる改正要綱案の審議に関与したが、本稿は委員当時の所属企業や推薦団体等の見解を代表するものではなく、筆者個人の見解であることをあらかじめお断りしておく。
注2 法制審部会や国会審議等で用いられた平成29年度の地籍調査の結果によれば、所有者不明土地の多くが「相続による所有権の移転の登記がされていないもの」(約65.5%)(法務省民事局参事官室・民事第二課「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明」(令和1年2月)162頁)であり、関係者の意識も、もっぱら相続登記をめぐる問題に集中する傾向があった。
注3 法律構成としては、所有権放棄の意思表示の結果ではなく、法律の定める所定の要件を満たした効果により土地所有権が国庫に帰属する、という形になっているが、同時に、この制度は「権利者の一方的な意思表示によって土地の所有権を放棄することはできないという解釈に親和性を有する」という解釈も示されており(令和3年3月23日衆議院法務委員会会議録18頁、小出邦夫政府参考人答弁)、今後の解釈論の展開が注目される。
注4 この制度に関しては、土地所有権を国に帰属させるための要件が厳しすぎる、という指摘も多かったため、施行後5年を経過した時点での見直し条項が盛り込まれている(相続土地国庫帰属法附則2項)。
注5 改正不動産登記法76条の4。「所有権の登記名義人が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合」に、登記官が職権で「その旨を示す符号」を表示することができるものとされた。
注6 改正不動産登記法76条の3。この制度は、相続等を原因とする所有権移転登記の申請義務を負う者が「所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、相続開始後3年以内の登記申請義務(改正不動産登記法76条の2第1項)を履行したものとみなされることとするものであり、申出があったときは、登記官が職権で当該申出をした者の氏名・住所等を所有権登記に付記することが予定されている。そしてこれにより、第三者がアクセス可能な相続人を早期に把握して必要な協議等に着手できるようになることが期待される。
注7 自民党・公明党の「令和3年度税制改正大綱」(令和2年12月10日)においても、不動産登記における登録免許税のあり方について、改正法の成案を踏まえ「令和4年度税制改正において必要な措置を検討する」とされている(大綱129頁)。
注8 これに合わせた経過措置として、施行日時点で法人が既に所有者として登記されている不動産についても、登記官が職権で会社法人等番号を追加する変更登記を行える旨が定められており(改正法附則5条5項)、この措置とシステム間の連携開始により、少なくとも法人に関しては登記名義人の住所変更未対応状態が一挙に解決することが期待される。
注9 国会審議においても、山野目章夫参考人(早稲田大学大学院法務研究科教授、法制審部会長)が、「今般提出されている法律案は、不動産登記制度に対する見方を点綴するということを促す要素が含まれているのではないかと感じます」(令和3年3月19日衆議院法務委員会会議録17頁)と述べられている。企業においても単なる「財産管理」の視点を超えた所有不動産の登記適正化への社会的要請が今後強まる可能性はある。
注10 改正法の多くの規定は公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されることされているが(附則1条本文)、相続登記の申請義務化等については「3年」(附則1条但書2号)、名称・住所変更登記の申請義務化については「5年」(附則1条但書3号)と、公布から施行までの間に一定の猶予期間が設けられている。

藤野 忠
西早稲田総合法律事務所 弁護士
1998年東京大学法学部卒業、JR東日本入社。在職中に旧司法試験に合格し、同社法務部課長等を経て、2019年西早稲田総合法律事務所を設立。法務部門のマネジメントや人材育成も含めた企業内実務への支援を幅広く行っている。また、産業界の諸団体を通じて債権法改正や著作権法改正の議論等に参画した経験を経て、2019年3月から2021年2月まで法制審議会民法・不動産登記法部会委員を務め、本稿のテーマに関する改正要綱案のとりまとめに関与した。
