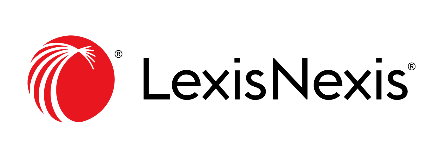2025年5月13日、企業法務の最新課題に迫るセミナー「法務の重要課題」が開催された。会場は、開業したばかりの虎ノ門アルセアタワーコンファレンス。5回目となる今回は、会場受講と同時にライブ配信を行うハイブリッド形式での開催となった。
経済安全保障法制から生成AI対応まで、多岐にわたる法的課題への対応が急務となる中、ベンチャーラボ法律事務所・代表弁護士の淵邊善彦氏を進行役に、異なる業界の法務責任者4名が登壇。さらにリーガルテック企業4社も加わり、実務に根差した活発な意見交換が繰り広げられ、満員の会場は終始熱気に包まれた。

2025年度施行の法改正への対応
冒頭、淵邊氏が2025年度施行の主な改正法令について概説。続くパネルディスカッションでは、法改正への具体的な対応策をめぐり活発な議論が交わされた。最初のトピックとして取り上げられたのが、2024年11月施行の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)。淵邊氏は、2025年3月にアニメ制作会社45社への行政指導が行われ、公正取引委員会の監視が強化されている現状を指摘したうえで、各社の取組状況について尋ねた。
守田氏 まず直面したのが“フリーランスの把握”という課題です。社名だけでは実態が見えにくい場合も多く、リスト化が課題となっています。当社では、経理への支払申請書にフリーランスかどうかのチェックボックスを設け、チェックが入ればフリーランス向け契約書テンプレートや条件確認プロセスへ移行するしくみを導入しました。申請者に依拠するため完全ではありませんが、“会社としてプロセスを踏んでいる”という説明責任を果たすうえで重要な一歩と捉えています。

守田 達也 氏
池上氏 当社は従来からSES(システムエンジニアリングサービス)のような開発業務委託が多いため、新法で求められる事項も充足した契約を締結しています。施行後も既存契約との大きな乖離はなく、契約審査ワークフローを通じて書面明示要件や報酬支払時期を取りこぼさないようにしています。
奥村氏 法改正について社内周知する中で、“相談窓口をどこにどう設置すればよいのか”といった質問が多く寄せられるなど、実務上の課題が明らかになってきた段階です。今後は、法務グループがハブとなり、各部門の対応事例を社内で共有していこうと思っています。
早川(拓)氏 施行を機に社内で取引状況を確認したところ、以前から「取引条件の明示」が適切に実施できていたことがわかり、安心しました。OB・OGや専門家との取引が多いこともあり、新法が意図する“フリーランスの立場の弱さ”という側面での手当てをする必要は、あまりないように感じています。
淵邊氏 サプライチェーン全体における管理という視点から、将来的には下請事業者のフリーランス活用状況にも気を配る必要性があります。また、エンタメ業界に続いて、次はソフトウェア業界など、フリーランス活用の多い分野から行政指導が入る可能性もあり、注意が必要です。
* *
育児介護休業法と雇用保険法の改正対応については、各パネリストとも人事部門の主導で進められていると述べたうえで、「働き方全般」に対する法務部としての取り組みを紹介した。
池上氏 現在、エンジニアには週1出社、コーポレート部門等には週3出社を適用するなど、創業期から柔軟な働き方を推進しており、法改正の影響は限定的と見ています。
守田氏 最近は、企業法務担当者の間ではワークライフバランスにとどまらない、“いかに私生活の中に仕事を柔軟に組み込んでいくか”という“ワークインライフ”についても議論されています。
奥村氏 グループ内に男女問わず子育て中のメンバーが多いため、在宅勤務を可能にするツールを導入しているほか、当社はシェアオフィス事業も運営しているので、法務メンバー自身が積極的に利用し、生産性向上の実証実験も行っています。

奥村 彰子 氏
早川(拓)氏 本社や営業部門ではフレックスやテレワークを導入済みですが、工場の生産部門ではテレワークが難しく、今後の課題です。
* *
施行間もない重要経済安保情報保護活用法についても話題に上がったが、情報取得の詳細や具体的な運用についてはまだ不明瞭な部分も多く、対応はこれからという状況が示された。
2025年度の重要トピック
セミナー後半では、近時の重要トピックとして、サイバーセキュリティ、個人情報保護法、公益通報者保護法、下請法の改正案、生成AIやリーガルテックの利活用など、豊富な話題について議論が展開された。
淵邊氏 サイバーセキュリティについては、“予算が乏しい中で何をどこまでやるべきか”という課題があります。サイバー対処能力強化法案(5月16日成立、23日公布)では、官民連携や通信情報の利用、アクセス無害化措置などが議論され、人権保護と安全保障のバランスが重視されています。
守田氏 ランサム攻撃を受けた際の身代金支払いの是非など、弁護士等も交えた意思決定プロセスの検討に法務も関与しました。攻撃側は莫大なリソースを有しているため、一企業が完全に対応するのは不可能だと思っています。重要なのは、企業として“やるべきことはやっていた”と言えること。多要素認証を組み込んだVPN、システムの適時のバージョンアップ、ECサイトの入力フォームの脆弱性診断という三つの主要な侵入経路については、必ず対策を講じる必要があると思っています。
池上氏 当社では、従業員のトレーニングに注力しています。社内非公開のプロジェクトで社員を対象とした侵入テストを行っており、どこまで侵入できるかを検証・改善する地道な作業を繰り返しています。また、身代金の支払先が反社会的勢力である場合の利益供与リスクも踏まえたケーススタディを実施するなど、法務の関与が必要となる局面もありました。
奥村氏 なりすましメールの社内訓練の頻度が昨年(2024年)より上がり、訓練用のメール内容もますます巧みになってきているので、個人のパソコンが狙われたときに備えて、定期的に意識を上げていく取り組みは不可欠だと感じます。
早川(拓)氏 情報セキュリティに関しては、情報システム部門や総務部門と連携し、委員会を設置して対応しています。最近は1回1問程度のプチ・Eラーニングを多頻度で実施し、従業員の意識を高める施策を開始し、一定の効果を上げています。

早川 拓司 氏
* *
淵邊氏 個人情報保護法も改正に向けて検討が進んでいます。この件で最近の社内の動きなどはいかがですか。
早川(拓)氏 当社では、キャンペーンの応募者情報など、代理店を介した個人情報取得が多いのですが、最近、委託先での不正アクセス事案が生じ、委託先の使用サービス(クラウド等)まで把握する必要性を痛感しました。
奥村氏 事業者への規制強化が進むと見込まれるので、現状の対応の見直しと、本人同意の確認や情報管理体制の棚卸しを進め、部門間での成功・失敗事例を共有しながら、改正に備えることが重要と考えています。
池上氏 名刺情報のようなビジネスコンタクト情報の円滑な利活用を期待しており、“同意規制のあり方”に注目しています。一方で、最近の情報漏洩に関する犯罪事案に鑑みると、罰金額の低さや懲役刑の執行猶予が認められやすい点で抑止効果が弱いため、刑事罰強化の必要性も感じています。

池上 光一 氏
* *
淵邊氏 改正公益通報者保護法の施行もまだ先ですが、現時点で注視している改正内容はありますか。
早川(拓)氏 「解雇または懲戒が公益通報を理由とすることを推定する規定」が気になります。解雇や懲戒に慎重にならざるを得ず、通報窓口である法律事務所との連携強化を検討しています。
守田氏 外部の弁護士や調査会社を活用して調査の透明性と公正性を高める方法を模索中です。やはり「推定規定」との関係で、人事評価も透明性を図る必要があるため、人事部と連携して啓蒙活動を強化する準備を進めています。
淵邊氏 このほかの注目点として、公正取引委員会が下請法違反への監視を強化しており、来年中に施行が見込まれる改正では①協議を適切に行わない代金額の決定の禁止と②従業員数基準の追加が主要な変更点です。②については従業員数の把握をどのように行うか、定期的なモニタリングや契約書での通知を求めるなど、対応が必要になるでしょう。
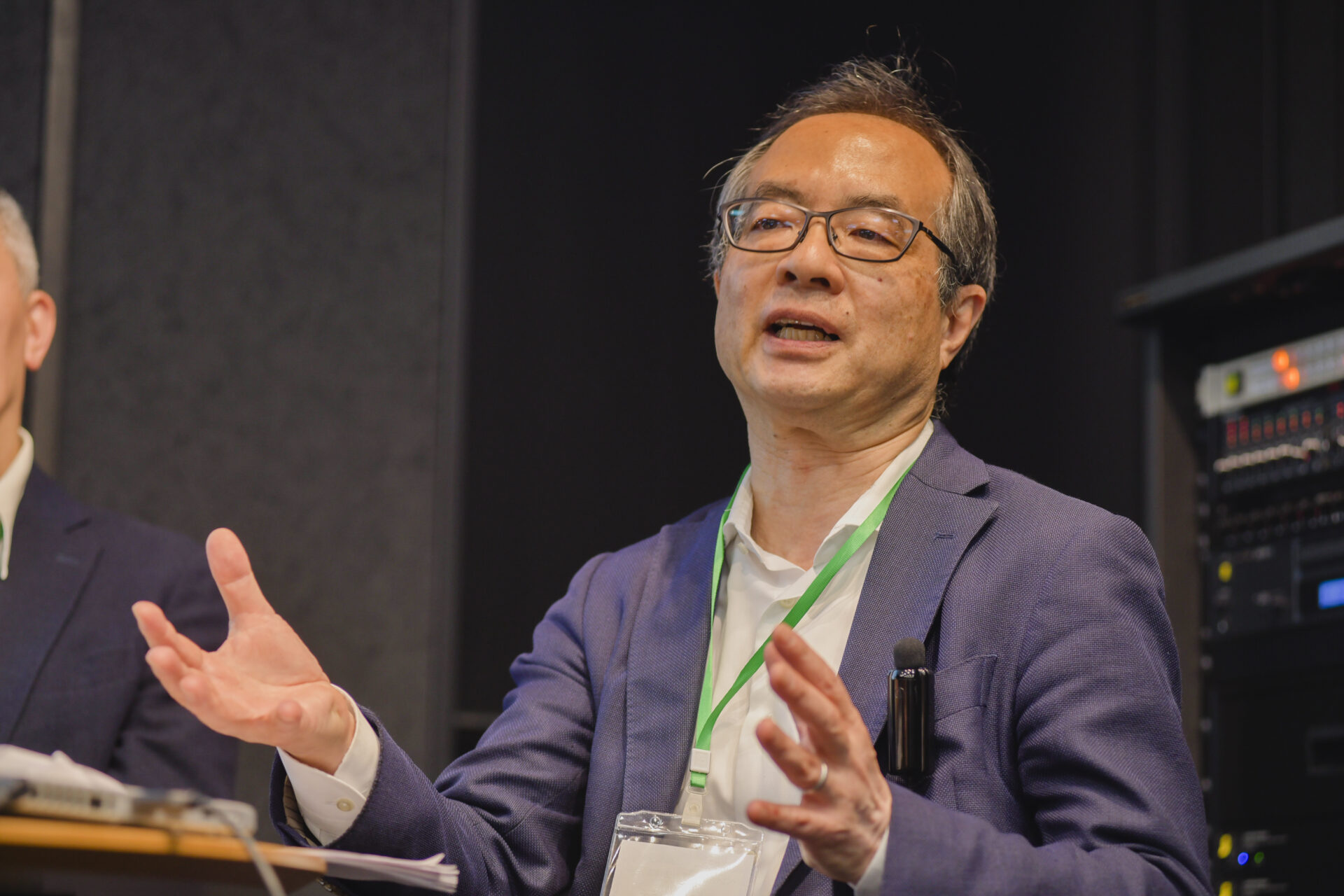
淵邊 善彦 弁護士
業務効率化の現状とリーガルテック活用状況
話題は業務効率化と生成AI・リーガルテックの活用に移り、議論に先立ちリーガルテック企業4社のサービスが紹介された。
まず、Sansan株式会社の井上祐輝氏が、あらゆる契約書をクラウド上で一元管理できる契約データベース「Contract One」を紹介。「全社員が契約情報を検索可能となり、処理速度と品質の両方を実現、組織全体の業務効率が向上する」と、そのメリットを強調した。

井上 祐輝 氏
現場の習慣を変える、契約データベース「Contract One」(詳細はこちら)
続いてEpiq(エピック)の早川浩佑氏と中島大輔氏が、「AIや機械学習テクノロジーを活用し、増大するデジタルデータの分析を迅速化、調査コストの最適化に貢献できる」という最新のデジタルフォレンジック技術と内部不正調査時の具体的フローについて解説した。

(左)早川 浩佑 氏、(右)中島 大輔 氏
Eディスカバリ支援から不正調査まで。世界80以上の拠点を持つデジタル・フォレンジックサービス(詳細はこちら)
レクシスネクシス・ジャパン株式会社の須江哲次氏は「ASONE 業務規程コネクト」の特徴として「社内規程と法律条文を紐付けし、法改正時にピンポイントで影響箇所を通知。条文単位での情報取得、施行日管理、対応状況の可視化、一元的な管理体制を支援します」と語った。

須江 哲次 氏
複数のモジュールで構成された、法務・コンプライアンス全般のオンラインデータベース/サポートツール(詳細はこちら)
最後に、MNTSQ株式会社の板谷隆平氏が新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」を紹介。「事業部サイドで発生する定型的・低リスクな案件をAIが前さばきし、高リスク案件のみ法務にエスカレーションすることで、法務部の業務効率化と事業スピード向上に貢献します」と説明した。

板谷 隆平 氏
契約を一気通貫でサポート、効率化と品質向上、ガバナンス強化を実現(詳細はこちら)
淵邊氏 多くの企業が生成AIの利用ガイドラインを策定していますが、重要なのは、全体的な業務効率化にどうつなげていくかです。リーガルテックの導入を情報管理部門や情報システム部門のみに任せてしまうと、利用面の配慮に欠けてしまうおそれがあります。業務フロー全体を考えると、法務部門が果たす役割は大きいと感じています。最近は、クライアントが生成AIで作成した契約書を見る機会が増えたのですが、従来の典型的な契約書とは異なり、実際の取引内容が反映された契約書に仕上がっているケースも見受けられます。AIの進化に伴いこうした新たな契約書が増加してくれば、契約書の作成やレビューのあり方は大きく変わる可能性があります。
池上氏 当社は2025年を“AIファースト”と位置づけ、社員が自ら生成AIを業務に活用しています。社内ナレッジを集約しているNotionのAI機能を活用しており、社内規程や法務の過去のやり取りを取り込むことで、これらを踏まえてAIが回答してくれるなど、日々の業務効率化に役立っています。
奥村氏 当社では情報の引き継ぎや記録保存が課題で、個人の職人技に依拠していた部分もありましたが、グループとして一定品質を保つためにCLM(契約ライフサイクル管理)を導入し、あらゆる情報を一元化する取り組みを開始しました。
早川(拓)氏 当社でも“情報の分散化”に対処するため、CLMを導入し、過去の検討経緯や関係部署とのやり取りがすべて残り、検索で参照できるしくみを構築しました。今後はAIを使ってFAQのような機能に進化させていくべく、ベンダーと相談を進めているところです。
法務組織・ナレッジマネジメント
早川(拓)氏 ナレッジマネジメントの試みとして、部内で定期的に“失敗事例の共有会”を開催しています。アナログな手法ですが、契約締結後に発覚した見落としなどを共有・議論することで、組織としてのナレッジ向上を図っており、実際に効果を感じています。
守田氏 リーガルテックの導入に際して、“どこまでをAIに頼ってよいのか、その判断は誰がするのか”という点が重要であり、外部の弁護士に関与してもらう必要もあります。企業が適切な手続を踏んで意思決定したことを示すためにも、外部弁護士のアドバイスを得るプロセスは重要です。
淵邊氏 客観的な意見や、経験に裏打ちされた総合的な専門性は外部弁護士の強みなので、法務部門と外部弁護士がお互いに切磋琢磨し、業務分担しながら、企業価値の向上につながる機能を連携して実現できるとよいですね。
2025年は法務に影響の大きい法令の施行は少ないものの、今回成立した各法令の施行に向けた対応に加え、今後議論が深まるであろう会社法の改正など、立法府や規制当局の動向には留意が必要です。
最新情報をフォローし、経営陣や事業部門へ浸透させていくのも法務の役割です。法務部門は“受け身”だと評されることもありますが、積極的に「この改正をこう活用すれば、より強い会社になる、より利益が出る事業部門になる」といった発信をしてほしいと思います。法務機能の充実と経営陣へのアピールを通じて、日本の法務部門全体の地位向上が図られることを願っています。

懇親会の様子

守田 達也
双日株式会社
CCO 兼 CISO 兼 法務、内部統制統括担当本部長

奥村 彰子
三井不動産株式会社
総務部 法務グループ グループ長

早川 拓司
カゴメ株式会社
法務部長

池上 光一
Sansan株式会社
執行役員 総務法務部 部長 兼 内部監査室 室長 兼 情報セキュリティ部

淵邊 善彦
ベンチャーラボ法律事務所
代表弁護士

井上 祐輝
Sansan株式会社
コーポレート本部 総務法務部 ビジネス法務グループ Legal Frontier Team

早川 浩佑
Epiq(エピック)
シニア・ディレクター/公認不正検査士(CFE)

中島 大輔
Epiq(エピック)
ディレクター/公認不正検査士(CFE)

板谷 隆平
MNTSQ株式会社
代表取締役/長島・大野・常松法律事務所 弁護士

須江 哲次
レクシスネクシス・ジャパン株式会社
コーポレートセールス チームリード