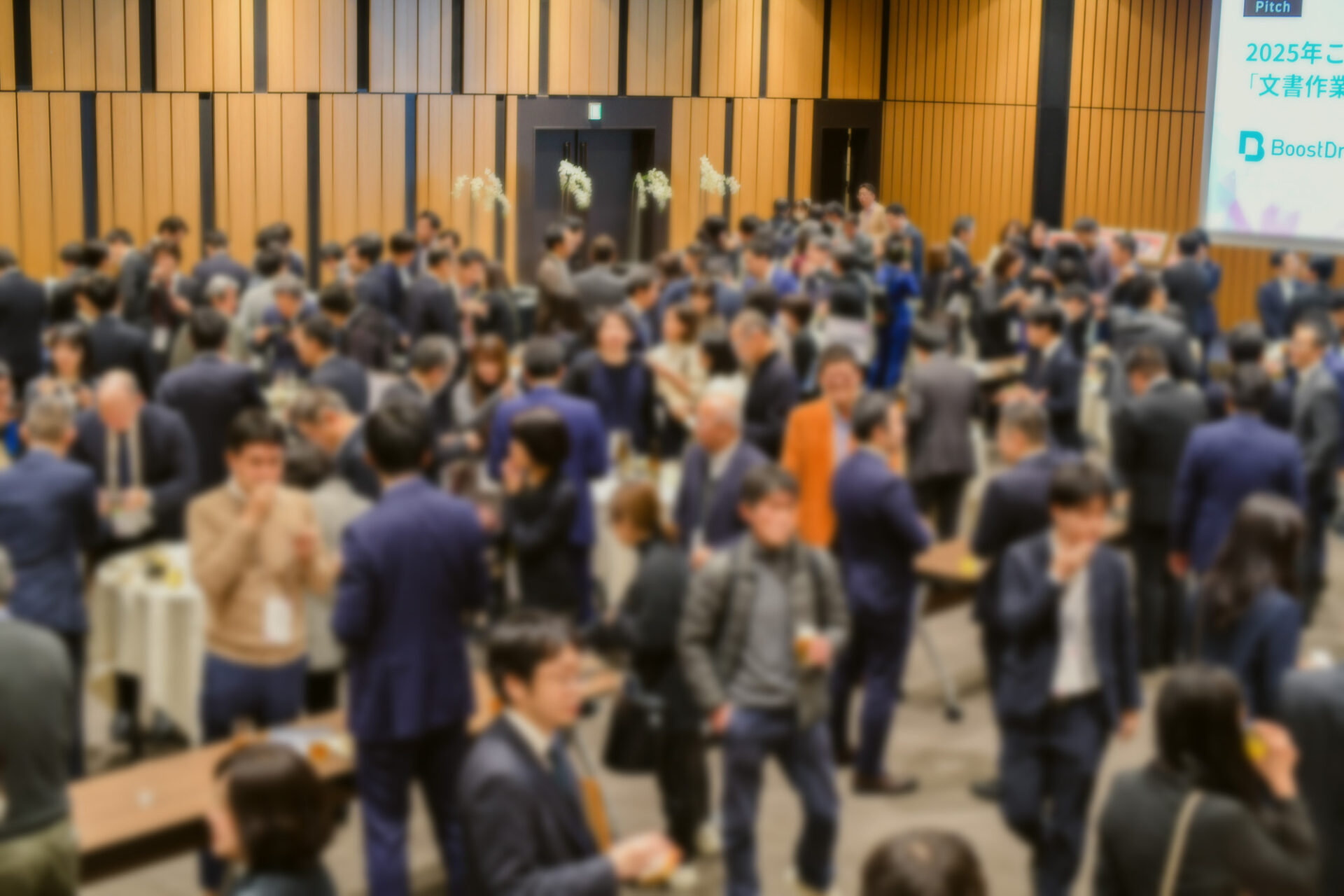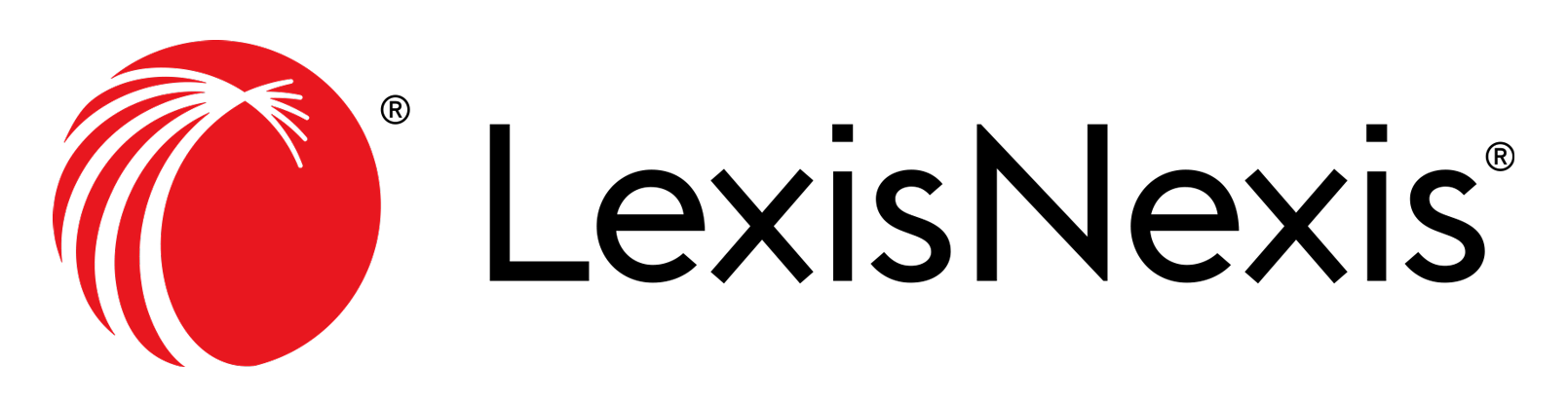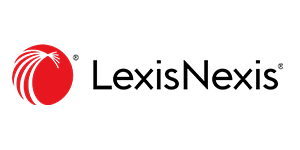2025年1月27日、赤坂インターシティコンファレンスにおいて、企業法務×弁護士のネットワークカンファレンス第2回「Business & Law CIRCLE 2025」が開催され、企業法務・コンプライアンス・知財部門の役職者約150名、弁護士約50名、そしてリーガルをサポートする企業の関係者が一堂に会した。
Business & Law合同会社主催、リーガルテック・コンサルティング企業5社共催による本カンファレンスは、昨年に引き続き2回目。プログラム前半では、企業法務の最前線で活躍する論者を迎えた座談会が2部構成で行われ、会場には多くの参加者が詰めかけた。

いま一度考えたい法務リテラシー~社内発信と体制づくりのヒント
プログラム第1部では、「いま一度考えたい法務リテラシー~社内発信と体制づくりのヒント」と題して、佐藤悠花子氏(日産自動車株式会社 グローバルエシックス&コンプライアンスオフィス Senior Manager)、藤本浩二氏(三井化学株式会社 総務・法務部 法務グループ グループリーダー)、岩井佑介氏(株式会社LIXIL Compliance&Ethics 部長)が登壇。以下の四つのテーマを巡り、活発なディスカッションが展開された。

法務機能”の立ち位置と体制
まず司会進行役を務めた岩井氏が、3社とも法務部門とコンプライアンス部門が分かれている点で共通するが、藤本氏は法務部門に、佐藤氏と岩井氏はコンプライアンス部門に所属していると説明。続いて各社の法務体制の特徴として、佐藤氏は「当社のコンプライアンス室はグローバルのコンプライアンス機能を担い、海外グループ会社と連携しつつ、さまざまな法的リスクに対する予防と発見・対応というコンプライアンス関連の施策に取り組んでいます。アジアやヨーロッパなど各リージョンに配置された法務・コンプライアンス担当者が傘下組織に方針を浸透させる体制ですが、たとえば人権等、一部領域では欧州の法規制が先行しているなど、各地域の法規制の進展度が異なるため困難も大きいですね」と同部の役割を語った。藤本氏は「当社の法務グループは3チーム体制で、各チームが特定の事業部を担当する一方、独禁法、安全保障輸出管理、贈収賄などの専門分野についてはチーム横断的に担当しています。コンプライアンス体制構築面では、三井化学グループでのグローバルポリシーがあり、これを遵守する受諾契約を原則すべての国内外子会社と結び、個社で社則が制定されるまでを法務グループが見届ける活動に取り組んでいます。また、グローバルでは世界4拠点の地域統括会社に法務機能がありますが、地域の法慣習に沿った体制構築の意味でもどこまで権限移譲できるかは今後の課題です」と続け、最後に岩井氏が「当社のコンプライアンス部門もリージョンごとに地域統括チームが設置され、現地チームに権限を移譲する体制が敷かれています」と述べ、3社ともグローバル展開に伴う課題と向き合いながら、柔軟な体制が構築されている実態をまとめた。
他部署でも「法務リテラシー・法務機能」を持ってもらうための体制や情報発信
寄せられる相談のリスク濃淡を分別・管理していくのが法務の悩みどころだと岩井氏が指摘すると、藤本氏が「当社では法務が原則として全契約を審査する“全件審査主義”を採用していますが、業務増加に伴いより効率的な業務遂行が必要な段階です。そのためには、事業部側の法務リテラシー向上が不可欠ですが、eラーニングだけでは不十分なので、効果的な方法を模索中です」と他部署の法務リテラシー向上に対する課題を提起。「eラーニングのほか、定期的なニュースレターの発行や、社内イントラネットを通じた情報発信をしています」(佐藤氏)、「法務部員がビジネスサイドの幹部会や新商品の会議に積極的に参加し、潜在的なリスクの早期把握と対応につなげています」(岩井氏)と、それぞれの取り組みが示された。

法務への案件相談に関する工夫
藤本氏が「担当チーム制を採用し、事業を理解したチームが相談対応することで的確な回答ができる体制を整えています。また、法務への依頼背景や確保したい事業目的等を正確に理解するため、契約類型に応じて、事業部側に回答してほしい質問が出てくる案件依頼システムを導入しています。依頼の差し戻し減少に効果がありました」と業務効率化の工夫を紹介。岩井氏は「チェックリストを活用し、低リスクの契約は法務の審査を省略しているほか、さまざまなリーガルテックを試している段階です。ただし、AIやツールにすべて任せるのではなく、最終的には“人による判断が必要”だと考えています」と続けた。
社内へのコンプライアンスの啓蒙手段や、研修方法での工夫
佐藤氏はポイントが二つあると指摘し、「一つ目は、実際に現場に出向いて情報を収集し、浮上した課題を研修コンテンツなどに活かしていくこと。二つ目は、研修やeラーニングの実施後はアンケートなどで効果を測定すること。研修効果を上げるには、こうしたPDCAサイクルを回していくことが重要です」と述べた。岩井氏も賛同したうえで、「リモートワークで現場とのつながりが希薄になりがちなので、現地研修を重視しています。また、コンプライアンス研修には“楽しく学ぼう”というマインドセットも必要だと思うので、イベントの開催や独自のキャラクターを活用した啓蒙活動も展開しています」と独自の手法を紹介。最後に3氏から、具体的テーマを設定し各事業部で行うワークショップ、アニメ・漫画の活用など、クリエイティブな取り組みの可能性が提起され、第一部が締めくくられた。
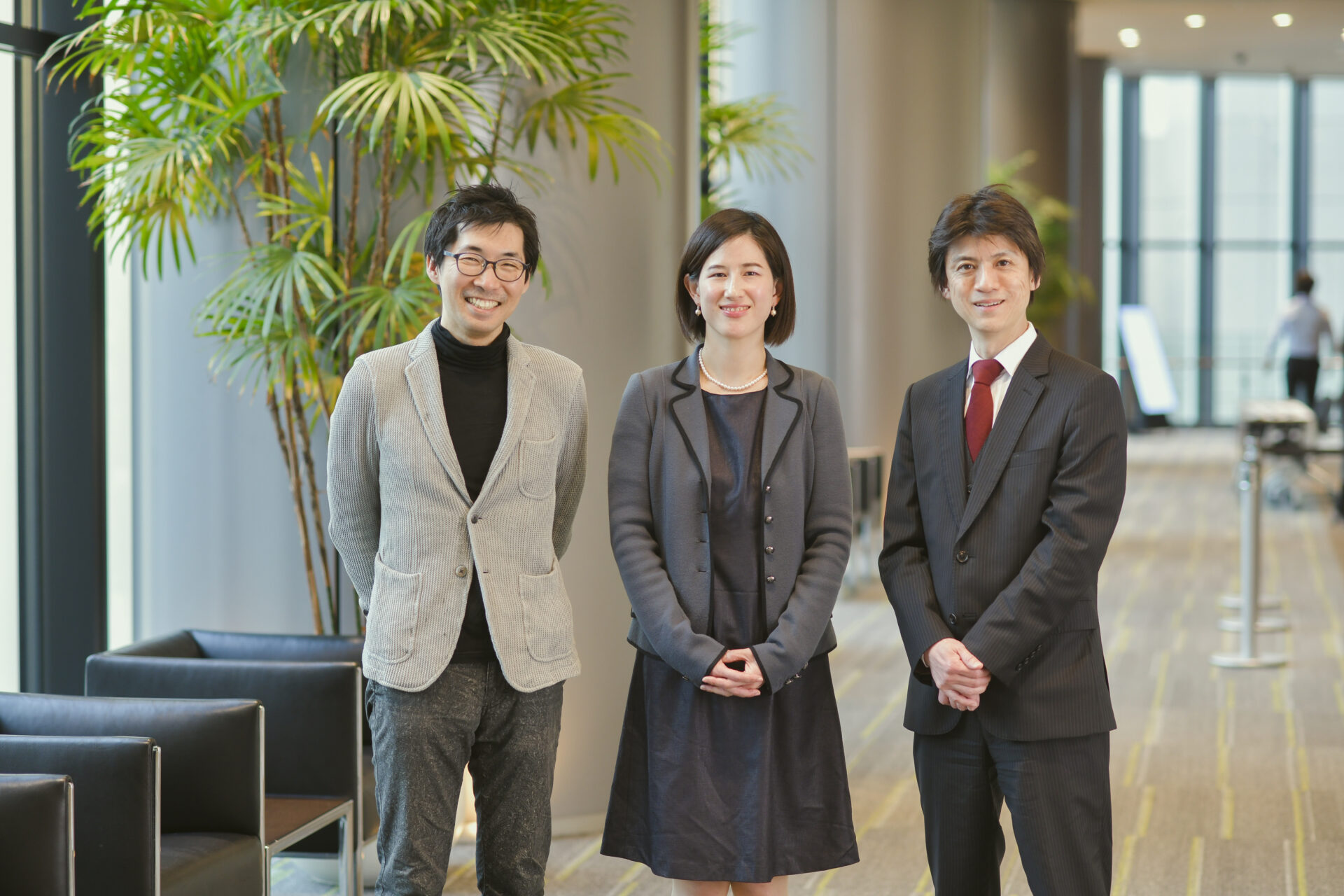
(左から)岩井 佑介 氏、佐藤 悠花子 氏、藤本 浩二 氏
協賛企業による最新リーガルテックの紹介
第1部と第2部の間、また懇親会のステージでは、共催リーガルテック企業によるショートピッチが行われた。
法務業務を人から組織へ 法務部に選ばれる「RICOH Contract Workflow Service(RICOH CWS)」
最初に登壇したリコージャパン株式会社の山中雄一朗氏は、「RICOH CWS」について、「現在の法務部門が直面する人材確保や業務効率化の課題に対して、効果的な解決策を提供するツール」だと説明。25年にわたって同社の法務業務改善に取り組んだ結果生まれた製品であり、その特長として、
・ 業務効率化:法務への契約相談から締結した契約管理まで一元管理
・ 低リスク案件の自動審査機能:法務業務の負荷を軽減し、現場部門への即応性を高める
・ ナレッジの共有と活用:組織内での知識共有を促進し、法務判断の質を向上させる
・ 専門性の発揮とキャリア形成支援:法務部門のメンバーが専門性を発揮しやすい環境を提供し、キャリア形成を支援
を挙げた。導入企業では相談の40%が自動審査機能により解決しており、ナレッジ蓄積のみならず、上司などに質問しやすいコミュニケーションツールとしても活用できるため、現在および将来の課題解決に有効と提示した。

山中 雄一朗 氏
進化する「Lexis+ AI™︎」 最新のリーガル ソリューションで法務業務を変革する
レクシスネクシス・ジャパン株式会社の須江哲次氏は、生成AIを利用したリーガルリサーチ・ソリューション「Lexis+AI(レクシスプラス エーアイ)」について、ChatGPTの使用例と比較しながら、その優位性と利便性を次のように紹介。
信頼のおける膨大な情報量を誇るLexis+をベースとし、チャット形式で気軽に使用できる点が、法務担当者に支持されている理由だと説明した。

須江 哲次 氏
2025年こそ「業務効率化」を進めるなら「文書作業」の見直しから
株式会社BoostDraft 共同創業者/CRO・弁護士の渡邊弘氏が、法律専門家向け総合文書エディタ「BoostDraft」について紹介。
・ Microsoft Word上で動作が完結、法的文書作成の無駄を自動化
・ 端末数に応じた月額費用で、費用対効果高く法務業務を効率化
・ インターネットは基本不要なため、機密文書データの外部送信なし
という特長をアピールし、「業務の非効率が解消され、弁護士や法務パーソンが本来の業務に集中できる環境作りに貢献します」と力説した。

渡邊 弘 氏
経営を担う法務出身者の視点で24年の振り返りと法務課題・展望
プログラム第2部では「経営を担う法務出身者の視点で24年の振り返りと法務課題・展望」をテーマに、鞍田哲氏(日揮ホールディングス株式会社 執行役員/ジェネラルカウンセル)、青谷賢一郎氏(株式会社ニトリホールディングス 上席執行役員/法務室室長)、林大介氏(パーソルホールディングス株式会社 取締役・監査等委員)による座談会が行われた。
2024年は法務にとってどのような年であったか
冒頭、司会進行を務めた林氏から、“2024年は法務にとってどのような年であったか”という問いが提示されると、鞍田氏は「多忙を極めた年」と総括。その理由として、地政学リスクの増大とサイバーセキュリティ対応の2点を挙げた。「米大統領選をめぐる政情不安や、ウクライナ情勢、中台関係の緊張は、グローバル企業に大きな影響を与えました。また、サイバーリスクも深刻化し、当社子会社もハッカーから身代金を要求される事態に直面、対応に追われました」と体験談を交えながら、ビジネス環境の悪化が法務に及ぼした影響を語った。青谷氏は、法務が担う業務領域の拡大と生成AIの普及という二つの観点を取り上げながら、「法務が担う業務量は年々増加していますが、法務人材の確保や育成は容易ではなく、業務効率化が各社共通の課題になっています。一方で、昨年は生成AIの普及が一気に進み、当社でもAIを活用した業務効率化に本格的に乗り出しています」と自社の施策を紹介。林氏は日経平均株価が史上最高値を更新した点に触れてから、「株式市場の活況を背景にM&Aが加速し、同意なき買収が増加しました。この流れを受けて、コーポレートガバナンスにおける法務の役割が増しているように感じます」と所感を述べた。

コーポレートガバナンスにおける法務の役割
次に、コーポレートガバナンスにおける法務の役割について問われた青谷氏は、取締役会の実効性向上に法務が寄与しており、「細かな議論は一切排除し、中長期の戦略的議論や海外出店戦略といった重大なテーマに議論を集中させるという方針転換を果たしました。この改革を主導したのが、事務局運営を担当する法務のガバナンスチーム。各取締役会メンバーに最適なアジェンダの年間スケジュールの設定から、毎回の取締役会における審議の所要時間、審議の順序といった細かい点まで、法務主導で改革を実行しました」と語り、鞍田氏も「取締役会の運営に法務的な観点は不可欠」と同意したうえで、「パーパス経営という文脈で議論する際も、法務の能力が求められています。当社の場合、リスクを付加価値に変えるビジネスモデルを持つだけに、リスクの軽減・回避における法務の重要性は増すばかり。今後はそうしたリスクへの対応を制度化し、経営者と近い距離で議論を重ねていく必要があります」と今後の展望を述べた。林氏は企業経営における法務の立ち位置について、「企業経営には収益性と健全性という二つの軸があります。収益性はCFOが、人材面はCHROが担当する。しかし、企業の健全性や倫理を語れる存在となると、CEOとジェネラルカウンセル(最高法務責任者)が適任でしょう。法務部門は企業の『守りの要』として、経営の健全性を担保する重要な部門といえます」と指摘した。
経営の立場から期待される法務の役割・取り組み
続いて、“経営の立場から期待される法務の役割・取り組み”について、鞍田氏は「会社の方向性を舵取りする、いわば羅針盤の機能を法務・コンプライアンス部門が担う時代。これまで以上に経営陣と近い距離で議論を重ねていく必要があります」と語り、法務の新たな使命を示唆した。青谷氏は、「従来の法務業務の多くは今後AIによって代替される可能性があるため、ヒトにしかできない役割は何かを真剣に考える必要がある」と指摘、“企業の良心の砦”としての法務の役割を提言した。そして「現代は、AIの法規制の問題に象徴されるように、環境変化のスピードが速すぎてルールがそれに追いついていない時代。そのような状況下で、その場その場で最も確からしい規範を見出し経営陣に問題解決の道を提示する能力は、他のコーポレート部門にはない法務特有の強みでしょう」と洞察を示した。この見方に対し、林氏も「コンプライアンスやインテグリティへの感度を高め、経営トップを右腕として支える役割を果たしていくべきですね」と、重責を担う法務の立場を強調した。
続いて、林氏から「攻め」の法務の役割について問題提起があり、鞍田氏は「グローバルガバナンスや地政学的リスクへの対応など、会社が抱える数多くの課題に対応する能力が求められています」と、リスクマネジメントの難しさについて指摘。青谷氏は「毎月開催される中長期戦略に関する役員・部門長会議で中核的な役割を担っており、たとえば海外展開におけるグローバルガバナンスの側面で、法務に大きな役割を果たすことが期待されています」と、経営のパートナー機能を担う法務の立場から発言した。
林氏が「最近の株式市場は会社の支配権を巡る争いの場になっていますが、M&Aの局面における法務の関与も広がっているように感じます」と述べると、青谷氏も「規模の大きい事業会社でも“買収される側になる”可能性を視野に対応していく必要がありますね」と同意し、鞍田氏は「当社もM&Aへの注力が見込まれ、それに対応できる法務組織の整備が求められています。まさに新たな役割であり、具体的対応策を含めて検討していかねばなりません」と緊張感をにじませた。
最後に法務担当者へのメッセージとして、青谷氏が「経営に資する役割が期待される中で、法務の強みは何なのか、それをいかにアピールしていけるか、皆さんと一緒に考えていきたい」と呼びかけると、鞍田氏は「法務パーソンは経営陣に対して耳の痛い指摘をできる人材であるべきで、精神的な強さも必要とされます」と、法務人材がいかに貴重な立場にあるかを強調。林氏が全体をまとめる形で、「法務の未来像が示される座談会となった」と述べ、締めくくりとした。
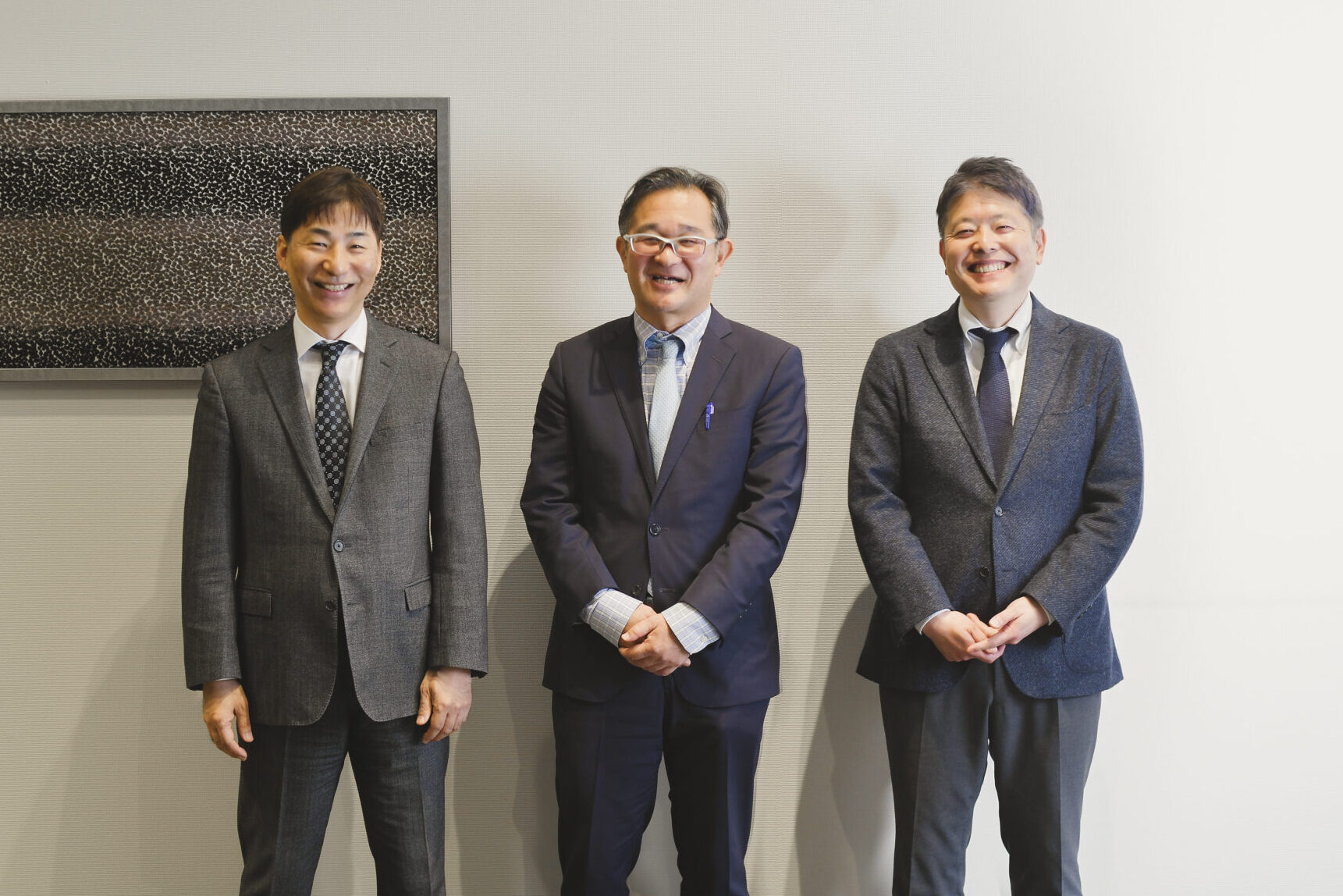
(左から)林 大介 氏、鞍田 哲 氏、青谷 賢一郎 氏
熱気あふれる交流会
座談会終了後、会場を移してビュッフェスタイルの懇親会が盛大に開催された。
乾杯の挨拶を務めたのは、GIT法律事務所の宮崎裕子弁護士。「皆さん、本年の抱負はもう決まりましたか?ご自身の可能性に蓋をせず、大きな夢を描き、その実現に向けて進んでください」と、新年最初のイベントにふさわしい言葉を贈り、「今年も新たな挑戦と成長の年となるよう願っています」と呼びかけた。

宮崎 裕子 弁護士
会場では各法分野のトークテーマを掲げた看板を目印に、参加者たちが興味のあるテーブルを回り、あちこちで活発な交流の場が生まれた。豪華賞品の当たる抽選会も行われ、会場は大いに盛り上がった。

また、会場では協賛企業であるリコージャパン株式会社、株式会社BoostDraft、株式会社Regrit Partners、レクシスネクシス・ジャパン株式会社、AOSデータ株式会社による、業務効率化に関するソリューションのブース展示も行われた。リーガルテックに関する最新動向への関心の高さを反映し、どのブースでも担当者の説明に熱心に聞き入る参加者の姿が見られた。

参加者からは、
・ 「これほど多くの法務関係者や弁護士と率直な意見交換ができる機会は貴重。かつての同僚と再会したり、さまざまな専門分野の弁護士に挨拶できたり、とても有意義な時間を過ごせました」
・ 「各社の取り組みや課題を共有できただけでなく、解決のヒントも得られました。明日からの業務に活かしたいと思います」
・ 「座談会のテーマが実務に直結するもので、とても興味深かった。もっと聞きたかったです」
など、熱意あふれるコメントが寄せられた。
和やかな雰囲気の中、会場は終始、歓談を楽しむ人々で熱気に包まれていた。今回の交流が新たな視点や気づきを得るきっかけとなり、法務業界の活性化につながることを期待させるカンファレンスとなった。