相次ぐ品質不正への問題意識
昨今、製品の品質を示すデータや検査結果のねつ造・改ざんなど、品質不正は後を絶ちません。
2015年頃から著名な国内メーカーにおける品質不正が発覚する事例が散見されるようになり、2017年頃には素材メーカーを中心に相次いで品質不正が発覚し、大きく報道されました。2017年12月4日には一般社団法人日本経済団体連合会が「品質管理に係わる不適切な事案への対応について」と題する声明を発出し、多くの企業において自主点検や調査が実施されましたが、残念ながらその後も日本企業による品質不正は根絶することはなく、現在に至っています。
品質不正は国内外の多種多様な業種・事業規模・ビジネスモデルの企業で発生・発覚しており、かつ研究・開発、製造、検査・品質保証等の各プロセスで不正が生じうるところ、あらゆるメーカーは品質不正とは無縁ではいられないのが実情と思われます。
なぜ品質不正が起こるのか?
不正の実行行為者の視点
製造業に携わる多くの方々は、「良い製品を作りたい」という気持ちで日々真面目に働いており、初めから品質不正をしたくて入社する人などいないと思います。それにもかかわらず、なぜ品質不正が発生してしまうのでしょうか?
この点に関し、米国の犯罪学者であるドナルド・R・クレッシー氏が提唱し、W・スティーブ・アルブレヒト氏が図式化した「不正のトライアングル」という理論があります。これは、“不正の機会”“動機”“正当化”という3要素が揃った場合に不正が発生するという考え方です。
品質不正の文脈では、データの改ざん等の行為を実行できる客観的な“機会”が存在する中で、「品質不正をしよう」という“動機”を持った従業員が自身の行為を“正当化”してしまった場合に、品質不正が発生するという整理となります。
たとえば、1人の検査担当者が検査結果を手書きで検査成績表等に記入する仕組みの場合には、当該担当者によるデータ書換えの“機会”があるということになります。
品質不正の“動機”は、「金銭的なメリットを追求する」といった利欲的なものではなく、「納期や目標・ノルマ等に関するプレッシャーやストレスから脱したい」といった類のものが多いと思われます。この点に関し、日本取引所自主規制法人が2018年3月30日に公表した「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」(以下「不祥事予防のプリンシプル」といいます)4頁では「不祥事につながった経営陣に係る問題事例」として、
「経営陣や現場マネジメントが製造現場の実態にそぐわない納期を一方的に設定した結果、現場がこれに縛られ、品質コンプライアンス違反を誘発」
というケース、5頁では
「経営陣から実態を無視した生産目標や納期の必達を迫られても現場は声を上げられず、次第に声を上げても仕方がないという諦め(モラルの低下)が全社に蔓延」
というケースが紹介されています。
「不正をしたい」と欲する“動機”を抱いたとしても、理性や良心のハードルが歯止めとして機能し、不正を思いとどまる人が多いと思います。しかし、“正当化”によりそのハードルを飛び越えてしまうことで、実行者は不正に及んでしまうと考えられます。
品質不正の文脈では、
「顧客との契約内容や仕様から少し逸脱していたとしても、安全性に影響しないため、問題はない」
「開発スケジュールや納期を遵守できないと会社全体に迷惑がかかるので、会社のためを思ってデータを書き換えた」
等と考えて自身の行為を正当化してしまうことが考えられます。
図表1 「不正のトライアングル」理論を用いた品質不正事案の分析例
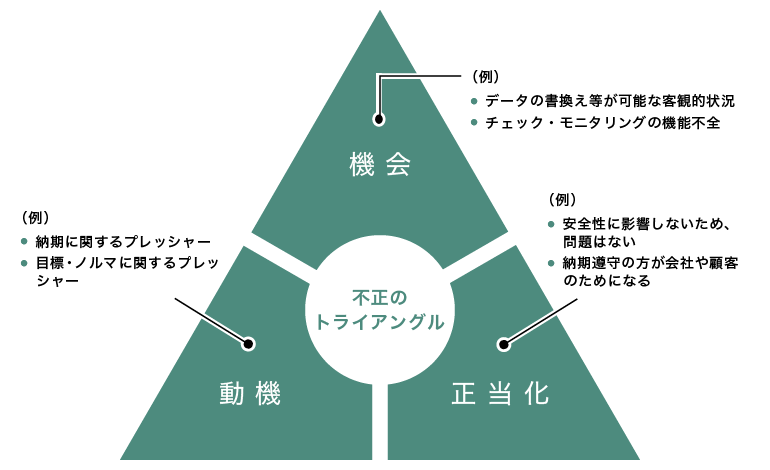
組織の視点
品質不正事案では、現場担当者等の個人のみに問題があるわけではなく、組織にも重大な問題があるケースも少なくありません。
たとえば、品質不正への牽制機能を働かせる組織構造や仕組みが不十分である場合には、品質不正が発生してしまう構造的なリスクがあると考えられます。この点に関し、不祥事予防のプリンシプル4頁では、
「製造部門と品質保証部門で同一の責任者を置いた結果、製造部門の業績評価が品質維持よりも重視され、品質保証機能の実効性を毀損」
「品質保証部門を実務上支援するために必要となるリソース(人員・システム)が不足」
というケースが紹介されています。
また、
・ 売上や利益を過度に重視して品質を軽視するような社内の傾向
・ メンバーの流動性が乏しく外部からの目が届きにくい閉鎖的な雰囲気
・ 意見や疑問の声を上げにくい空気感
など、組織風土・組織環境の問題が品質不正を助長する土壌になってしまうことも考えられます。
平時のリスクマネジメントの要諦
品質不正のリスクはあらゆる製造業に内在していると考えるべきであり、そのリスクをいかに低減し、管理していくかが平時の取り組みのポイントです。
品質不正を実行しうる“機会”の解消
品質不正を実行しうる“機会”を解消する方法としては、
・ 検査の自動化
・ データの改ざん防止プログラムの導入
・ 検査結果のダブルチェック
・ モニタリングの強化
等が考えられます。
不正の“機会”を完全になくすことができれば、理論的にはどんなに不正の動機を持った従業員がいたとしても不正は発生しないことになりますが、現実的には不正の“機会”をゼロにすることは極めて困難です。たとえば、研究・開発から製造・検査までの一連の工程をすべて自動化することは、コストや技術に照らして実現困難またはそもそも実現可能性がないケースがほとんどかと思います。
そのため、人的・金銭的リソースとコストとを勘案したうえで、実現可能な範囲で不正の“機会”を解消する仕組みを整備しつつ、他の不正予防策も並行して講じ、全体として不正が発生する可能性を最小化すべく尽力するというのが現実的かつ実践的なリスクマネジメントであると考えます。
不正の“動機”・“正当化”につながりかねない状況の改善
顧客・取引先や経営陣・管理職からの納期やノルマ等に関する過度なプレッシャーは品質不正の“動機”を抱かせる危険があり、他責化による“正当化”にもつながりかねません。
このような不正の“動機”・“正当化”につながりかねない状況を改善することで、品質不正のリスクを低減することが可能です。具体的には、他社事例や自社の実情を踏まえ、顧客・取引先との契約関係や社内の目標設定・指揮命令・コミュニケーションの見直しを検討することが考えられます。
また、役職員に対して継続的かつ実効性の高いコンプイアンス研修を実施し、役職員個人が安易に品質不正の動機を抱いたり、正当化をしたりしないよう教育していくことも肝要です。
風通しのよい組織風土の醸成・心理的安全性の確保
品質不正の背景事情となりうる組織風土の問題を改善することも、品質不正の予防策として有効と考えられます。閉鎖的な組織風土の対局にある風通しの良い組織風土のもとでは、品質不正やその隠蔽を予防することが期待できます。
また、昨今“心理的安全性”という言葉がさまざまな場面で用いられていますが、不祥事予防の観点からも従業員の心理的安全性の確保は非常に重要です。
・ 自身が疑問に思ったことを声に出せる環境
・ 過度なプレッシャーやストレスフルな職場環境に疑問を呈し、意見を言える雰囲気
を整えることは、品質不正を含むあらゆる不祥事に通底する予防策と考えられます。
社内の不正発見ルートの実効性のある運用
品質不正のリスクをゼロにすることが困難である以上、早期に品質不正の芽を発見できる仕組みを整備することも重要です。
品質不正が発生してしまったとしても、社内のルートでそれを発見することができれば、自社の不正を自社で発見し、解決するという意味での“自浄作用”を発揮するチャンスがあります。他方、品質不正の情報が監督官庁や報道機関等に内部告発されてしまった場合には、社内で当該不正を関知できないまま、突然監督官庁による調査を受けることになったり、スクープ記事が公表されたりすることになり、企業にとっては不意打ちを受けるような形になってしまうおそれがあります。そのため、社内の不正発見ルートの実効性確保はリスクマネジメントの観点から非常に重要です。
社内の不正発見ルートとしては、
・ 通常のレポーティングライン
・ 内部監査
・ 内部通報制度
等が考えられます。特に内部通報制度には、不正発見のための“最後の砦”としての機能が期待されるところであり、
・ 品質不正に特化した通報窓口の新設
・ 社内リニエンシーや通報義務を含む通報を促進する仕組みづくり
など、内部通報制度の機能強化や実効性確保に向けた施策も検討に値します。
有事のクライシスマネジメントの要諦
品質不正事案において求められる危機対応
ひとたび品質不正事案が発覚すると、企業は様々な対応を迫られることになり、時としてビジネスを揺るがすような危機的状況に陥ってしまうこともあり得ます。具体的には、以下のような対応が必要になる場合があります。
(1) 顧客・取引先対応
顧客・取引先との契約違反に該当するような品質不正においては、顧客・取引先に対しての謝罪・説明・補償の検討を要します。製品の安全性に問題がある場合には、リコール(自主回収)の検討が必要となります。
(2) 監督官庁対応
業種や製品によっては監督官庁による調査・報告徴収命令等への対応が必要となることがあります。重大事案では、企業は行政処分(営業停止命令、許認可の取消処分等)を受けることもあり得ます。
(3) 民事訴訟対応
品質不正事案においては、消費者や取引先からの損害賠償請求訴訟、株価下落を背景とした株主による証券訴訟、役員責任を追及する株主代表訴訟等、様々な民事訴訟が提起される可能性があります。グローバル展開をしている企業については、海外においてクラスアクション(集団訴訟)が提起される事態もあり得ます。
(4) 刑事手続対応
製品のデータの改ざん等の行為については、事案によっては品質等の誤認惹起行為(不正競争防止法2条1項20号)として、刑事罰の対象になり得ます。また、経営陣を含む役職員が逮捕・勾留されたり、企業が捜索・差押えを受けたりするなど、捜査当局による捜査が実施されることもあり得ます。
(5) その他の対応
その他、企業不祥事全般で問題となりうる広報対応、マスコミ・問合せ対応、懲戒手続・役員の責任追及等の社内手続については、品質不正においても問題になり得ます。
出発点としての事実解明
さまざまな危機対応において、事実解明が出発点となります。顧客・取引先等のステークホルダーへの説明、監督当局への報告、民事訴訟・刑事手続への対応、社内手続等、あらゆるプロセスにおいても“事実”が何であったかを起点とする必要があります。
また、事実を出発点にしなければ、適切な原因分析や再発防止策の策定はなし得ません。この点に関し、日本取引所自主規制法人が2016年2月24日に公表した「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」(以下「不祥事対応のプリンシプル」といいます)の原則1では「不祥事の原因究明に当たっては、必要十分な調査範囲を設定の上、表面的な現象や因果関係の列挙にとどまることなく、その背景等を明らかにしつつ事実認定を確実に行い、根本的な原因を解明するよう努める」と定めており、背景事情を含めた確実な事実認定の重要性を読み取れます。
昨今は調査委員会が事実調査を行い、原因分析や再発防止策の提言を行うプラクティスが定着しつつありますが、特に組織ぐるみの品質不正や経営陣の関与が疑われるような事案では、独立性を確保した委員会による客観的・中立的な調査の必要性が高いと考えられます。
情報開示の重要性と難しさ
不祥事対応全般において企業による情報開示は重要ですが、品質不正事案においては、多数のステークホルダー(顧客や取引先等)が情報を求めているケースが多く、情報開示の重要性は非常に高いといえます。
不祥事対応のプリンシプルの原則4では、「迅速かつ的確な情報開示」を行い、透明性の確保に努めるよう定められていますが、品質不正事案においては事案の規模や複雑さ次第では、迅速性と的確さの両立が困難なケースもあり得ます。企業の説明が二転三転しないよう正確性を吟味しつつ、確定的な情報を継続的に発信するなど、真摯な姿勢が求められるでしょう。
まとめ
品質不正事案がひとたび発覚すると、企業は危機的状況に陥ってしまうことは他社事例に関する報道等を見るとおわかりになるかと思います。自社で品質不正が発生する可能性を最小化すべく、平時に適切な予防策を講じ、不正の芽や温床を可能な限り早期に発見できる仕組みを整備したうえで、万一品質不正が発生・発覚してしまった場合には、十分なリソースを充てて真摯にクライシスマネジメントに取り組むことが品質不正対策の要諦であると考えます。
具体的な方策については、不祥事予防のプリンシプル、不祥事対応のプリンシプルや他社事例を参考にしつつ、自社に最適な方法を模索していく必要があります。より詳細な内容や最新実務は、オンラインセミナーで解説しておりますので、ご受講いただけますと幸いです。

坂尾 佑平
三浦法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士・公認不正検査士
2011年東京大学法科大学院修了。2012年弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所入所。2014年CFE(公認不正検査士)資格、2015年認定コンプライアンス・オフィサー資格を取得。2018年University of Pennsylvania Law School (LL.M. with Wharton Business & Law Certificate) 修了、Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr 法律事務所(ワシントンD.C.)勤務。2019年ニューヨーク州弁護士登録。2020年三井物産株式会社法務部出向、企業危機管理士資格を取得。2021年3月より現職、同年中級食品表示診断士資格取得。危機管理・コンプライアンス、コーポレートガバナンス、ESG/SDGs、紛争解決等を中心に、広く企業法務全般を取り扱う。
