はじめに
2020年12月25日、2019(令和元)年6月に成立・公布された改正独占禁止法が施行注1された。1977(昭和52)年改正により導入された課徴金制度を約40年ぶりに見直す改正であり、実務への影響は大きい。
施行から約10か月が経過するが、改正の多くはカルテルや談合を疑われた企業が公正取引委員会(以下、「公取委」という)による審査手続の過程で利用する課徴金減免制度や判別手続、あるいは最終的に課せられる課徴金等に関するもの、すなわち有事の際に関わるものであるので、いまだ改正法が適用される実務を目の当たりにしたことはないという企業が多いと思われる。
他方で、改正された課徴金減免制度のように、平時からきちんと制度を理解(インプット)しておかないと、有事(アウトプット)の際、特に初動において適切な審査対応ができないという改正項目や、判別手続のように有事の際に制度を利用するためには平時からの準備が不可欠な改正項目が多いため、平時からの準備・対応は不可欠である。筆者自身も、施行前後から、独禁法コンプライアンスの実務の(細かい点も含めた)見直しのご相談を受けることが多い。
本稿では、改正を踏まえたこれからの実務について検討する。
改正法が実務に与える影響
いまや、独占禁止法は企業にとって最優先にコンプライアンスが求められる法分野の一つであるが、それは違反した場合のペナルティその他の不利益の甚大さゆえである。とりわけ、不当な取引制限のうちカルテルや談合といったハードコアカルテルは課徴金額が高額になることが多く、企業にとって最も大きなリスクとして捉えられている。
もっとも、改正前の独占禁止法では、違反行為の実行期間にかかわらず課徴金の算定期間が最大3年に限定されているなど、欧米の競争法に比べると相対的にペナルティは小さくなる傾向にあり、国際カルテルのケースなどでは、欧米の競争当局等対応を最優先課題とした戦略がとられ、日本での対応は二の次とされることが少なくないとの指摘もあった注2。
こういった状況等も踏まえ、令和元年改正では、カルテルや談合(不当な取引制限)に課せられる課徴金が高額になる方向での規制強化がなされた。企業にとってはリスクが増大し、今まで以上にコンプライアンスの徹底が求められるようになったといえる。
また、カルテルや談合に関しては、2006(平成18)年1月に課徴金減免制度(リニエンシー)が導入されて以降、実務では、いかに他社に先んじて同申請を行い課徴金の減免を得るかが初動における最重要課題とされてきたところ、令和元年改正では、かかる課徴金減免制度についても大幅な見直しがされている。企業としては、有事の際に適切に同制度を利用できるように、あらかじめ新制度の内容を正確に理解し、備えておく必要性は高い。
さらに、独占禁止法の改正そのものではないものの、関連する改正として、規則(公正取引委員会の審査に関する規則)の改正により新たに「判別手続」が導入された。改正の議論過程において、諸外国で認められている“弁護士・依頼者間秘匿特権”を我が国にも導入すべしとする経済界等からの強い要望を受けて導入された新たな制度であるが、公取委による立入検査というまさに有事の場面での即座の利用が予定されており、また、その利用条件の厳格さゆえに、有事の際に利用するには平時からの準備が必要になる点で、やはり実務への影響は大きい。
本稿の目的
令和元年改正の内容は、大きく図表1の①~④のとおりである。また、上述のとおり、独占禁止法の改正ではないが、規則および指針等により整備された⑤も関連する改正として押さえておくべきである。
図表1 改正の概要
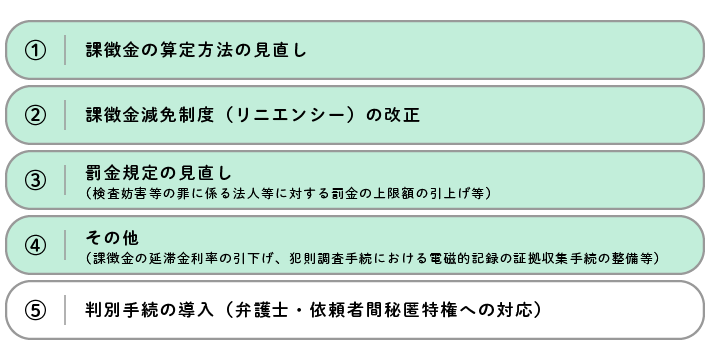
本稿は、このうち実務への影響が特に大きいと考えられる①、②、⑤について、改正がもたらす企業法務実務への影響を、2回に分けて考察するものである。
改正の内容については、既に施行の前後を通じて至る所で解説されているところであるので、本稿で詳細に触れることはせず、本稿では、改正項目の中でも実務的に影響が大きいだろうと思われる点をピックアップして、「改正によって実務がどのように変わっていくのか」にスポットを当てて検討を行いたい(なお、最も影響が大きいのは不当な取引制限であるため、カルテル・談合のケースを念頭に置いて検討を行う)。
なお、検討の前提として、独占禁止法の改正に伴って改正された規則や新たに公表または改定されたガイドライン等を整理しておくと、図表2のとおりである。
図表2 関連する規則・ガイドライン等の改正・公表等
| 2020年7月7日 |
・ 「事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容が記録されている物件の取扱指針」の公表 ・ 「独占禁止法審査手続きに関する指針」の改定 |
| 2020年8月~9月 |
・ 独占禁止法施行令等の関係政令等が閣議決定(8/28)、公布(9/2) ・ 「調査協力減算制度の運用方針」の公表(9/2) |
| 2020年12月25日 |
・ 「公正取引委員会の審査に関する規則」の改正 ・ 「課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則」の改正 |
課徴金の算定方法の見直し
改正の概要
改正前の課徴金制度は、一律かつ画一的に課徴金が算定される硬直的な制度となっており、複雑化する経済環境のもと、多種多様な態様で生じる違反行為に適切な課徴金を課せないという問題意識を前提に、実態に応じた適切な課徴金を課すべく改正がなされた注3。基本的には課徴金が増額される規制強化方向での改正であり、違反行為に対する抑止力が強化されたといえる。
改正の概要は、図表3のとおりである。課徴金は、①算定基礎となる売上高に②算定率を乗じて算出されるが(なお、③課徴金減免申請が認められた場合は、そこから減免分が控除される)、令和元年改正では①②のいずれもが拡大する方向で改正がなされた。
図表3 課徴金算定方法の見直しの概要
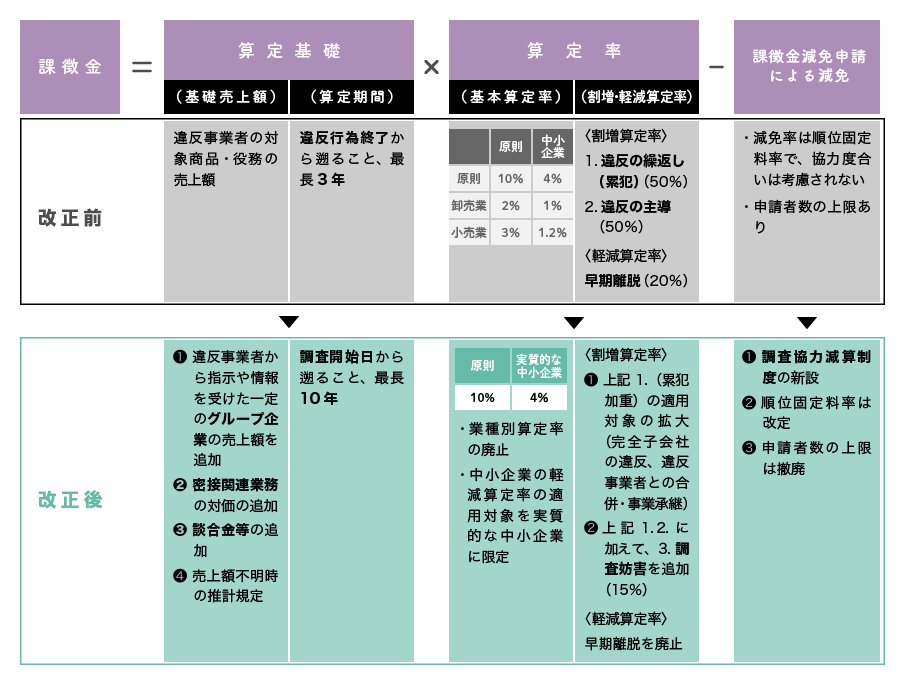
(1) 算定基礎の見直し
まず、①算定基礎は、(a)事業者が違反行為の実行としての事業活動を行った日(始期)から、当該事業活動がなくなる日(終期)までの期間(実行期間)における(b)違反行為の対象となった「当該商品又は役務」の売上額とされるが、この(a)算定期間と(b)基礎となる売上額のそれぞれについて改正がなされている。
(a) 算定期間
算定期間については、改正前まで、「違反行為終了」から遡ること最長3年という上限が定められていたが、「調査開始日」注4から遡ること最長10年に改められた(起算点も変更されていることに留意。令和元年改正後の独禁法2条の2第13項・第14項。以下、特に断りのない限り、「独禁法」とある場合には令和元年改正後、つまり現行の同法を指す)。
これは、長期間にわたる違反行為であっても課徴金が3年に限定されることで、(違反行為による不当利得すら吐き出させられない点で)“やり得”が生じているという問題点を踏まえた改正である注5。他方で、あまりに長期の違反について課徴金を算定するとなると、事業者に帳簿書類等が残存しておらず計算ができないケースも生じうると考えられたことから、帳簿書類等の法定保存期間を踏まえて10年が上限とされた。この点は、上限を設けていない欧米諸国等の法制とは異なる。
なお、算定期間の改正に関連して、実務上2点押さえておくべきである。1点目は、施行日をまたがる違反行為の課徴金がどのように算定されるかであり、図表4を参照されたい注6。
2点目は、算定期間の改正ではないが、「除斥期間」の延長である。除斥期間とは、違反行為の実行期間終了日から当該期間が経過すると排除措置命令や課徴金納付命令を課せられなくなる期間をいうが、改正前は5年であったものが7年注7に改正された(独禁法7条の8第6項、同7条の9第4項、同8条の3、同20条の7)。
図表4 経過措置(旧法と新法の適用関係)
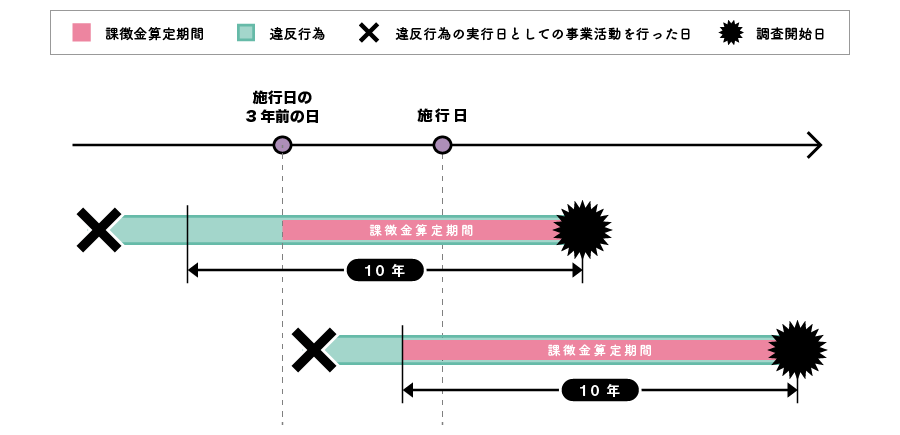
(b) 算定基礎となる売上高
基礎となる売上額は、違反行為の対象となった「当該商品又は役務」の売上額を指すが、改正前は法人格単位でこれを算定していたため、違反事業者自体には売上がなく、その子会社等が違反対象商品等を販売し売上をあげているようなケースでは、当該子会社等の売上に課徴金を課すことができなかったところ、改正によって企業グループ単位で基礎売上額を算定する種々の見直しがなされた。
あわせて、入札に参加しない見返りに受けた談合金等や、入札に参加しない代わりに落札者の下請に入った業者の下請業務(密接関連業務)にかかる売上等、改正前では課徴金を課すことのできなかった利得が課徴金の査定基礎に含まれる注8ようになった(独禁法7条の2第1項3号・4号)。
(2) 算定率の見直し
改正前は、図表3上段のとおり業種によって異なる算定率が適用されていたが(業種別算定率)、廃止された。
また、中小企業には軽減算定率が適用されるところ、適用対象が実質的な中小企業に限定されるとともに、違反した中小企業が大企業グループに属している場合の適用が排除された(独禁法7条の2第2項)。
このほか、改正により、早期離脱の軽減算定率は廃止され、他方、算定率の加重要件についても、累犯加重の適用対象が整理されるとともに、主導的役割加重は適用対象が拡大された。
改正を踏まえた実務の変容
(1) カルテル・談合の防止策のさらなる強化
まず何より、企業にとっては課徴金リスクが大幅に増大したことで、カルテル・談合の未然防止が今まで以上に重要な経営課題となったといえる。
すべての企業にとって、算定期間の延長(3年→10年)により、長期にわたる違反行為に課せられる課徴金の金額は単純に最大3倍以上となり、また、たとえば商社といった卸売業者やスーパーマーケット・百貨店といった小売業者にとっては、業種別算定率が廃止されたことで課徴金額は3倍、5倍に跳ね上がった。さらに、適用範囲が厳格化されたことで適用対象から漏れた中小企業は、軽減算定率の適用を受けられず、課徴金額は2倍以上に増額することとなった。
そのほか、算定基礎となる売上高の範囲拡大や割増算定率の適用範囲拡大および早期離脱による軽減算定率の廃止もまた、いずれも課徴金額の増額をもたらす改正である。
加えて、課徴金制度の改正ではないが、除斥期間が延長されたことで、従前より過去の行為について立件されるリスクも高まった。
企業としては、不当な取引制限(カルテル・談合)のリスクが増大したことを踏まえて、他社との接触ルール等の社内ルールや規程等を新たに整備し、または見直す必要がないかをチェックするなど、これまで以上にカルテル・談合防止のためのコンプライアンス体制を整備・強化するとともに、役職員への研修等を通して、リスクが増大したことを社内に周知する必要があるだろう。
また、課徴金の算定期間延長および除籍期間の延長を踏まえ、社内調査・監査を行う場合の期間設定を見直すとともに、過去の資料に関する管理・保存体制(文書保管規程等)を見直すべきである。
さらに、算定期間が延びたことで、長期継続する違反行為を早期に発見する重要性がより一層増したともいえる。違反を放置すればするほど課徴金はどんどん増大するため、違反を早期に発見するのみならず、当該違反をいち早く停止して課徴金減免申請を行うことが重要である。そのため、内部通報制度がきちんと機能しているかを見直すとともに、場合によっては社内リニエンシーといった制度の導入を検討することも考えられる。
(2) “グレー事案”への対応
(1)は平時の実務への影響であるが、改正は有事の際の企業の対応にも影響を及ぼす。まず、内部通報や社内調査または公取委の立入検査によって独禁法違反の可能性のある行為の存在が判明した場合、企業は、対応方針(課徴金減免申請を行うか、争うか等)を決定するべく、当該行為が独禁法に抵触するかどうかをまず検討することになるが、実務上、違法か適法かの法的解釈が微妙な“グレー”の事案がある。そのような事案の場合、法的に適法と解釈しうる余地があるとしても、訴訟で主張が認められるかどうかを弁護士とともに精緻に分析しつつ、違法と認定された場合のリスクの大きさに鑑みて、保守的に判断を下さざるを得ない(違法という前提で課徴金減免申請を行う)ケースが従前よりも増える可能性がある。
取締役としては、課徴金減免申請を行わなかったまたは遅かったことを理由に役員責任(任務懈怠責任)を問われる可能性があること注9も踏まえると、なおさらこの傾向が強まる可能性もある。
(3) 公取委による審査手続の長期化
また、これまでの公取委による審査実務では、違反行為に関わったとされる従業員に対する供述聴取において審査官が作成する独白形式の供述調書(自白調書)が、違反行為の立証の中心とされてきたところ(供述調書中心主義)、(少なくとも筆者の経験では)かかる自白調書の作成においては、違反行為期間中の会合や他社との接触等の一つひとつについて具体的に聴取が行われ、調書化されることが多かった。
改正前は、課徴金の算定期間が最長3年であることを踏まえて、いわゆる“「遅くとも」認定”注10をする前提で直近3年間の会合等のみが調書化されていたが、今後も同様の運用がなされるのであれば、3年を超える長期の違反行為の場合、最大で10年の間に開かれたすべての会合等について一つひとつ聴取し調書化することとなり、審査手続期間が長期化する可能性がある。
他方で、次回解説する課徴金減免制度の見直しにより、公取委の審査実務が供述調書中心主義から脱却し、事業者の側に積極的に報告や証拠提出させることで証拠を固める方向に変わるのであれば(実際、その方向での実態解明が期待されていると考えられる)、審査手続期間の大幅な増大というのは杞憂に終わるかもしれない。
(4) 違反行為の“一連性・一体性”の争点化
長期にわたる違反行為では、担当者の変更や一部の参加企業の違反からの離脱といった出来事を契機に会合の名称や参加企業が変化したり、調整行為や情報交換が行われない空白期間を経つつ断続的に行われたりするケースがある。
そのような違反行為の場合、罰金・制裁金の算定期間に上限がない欧米諸国などでは、時効等との関係で、連続した一体の違反行為といえるのか、それとも複数の別個の違反行為なのかが争われることがある。
日本では、これまでは直近3年間のみが問題とされたため、この点はあまり問題とならなかったが、今後は、少なくとも10年間は遡ることとなる結果、この点が争点となることがありうる。事業者としては、できる限り別個の違反行為であることを主張立証し、古い違反行為については除斥期間の経過を主張することになるだろう。
* *
以上、今回は、課徴金の算定方法の見直しを中心に、令和元年改正独禁法の概要と実務への影響を紹介した。次回は課徴金減免制度(リニエンシー)の改正と、判別手続の導入について実務への影響を検討する。
→この連載を「まとめて読む」
- 全面施行に先立って、繰り返し違反に対する課徴金の割増算定率に係る規定の改正(令和元年改正全面施行後の独禁法7条の3第1項)、および検査妨害等の罪の法人等に対する罰金額の上限の引上げ等(同94条の2、95条1項・2項)は2019年7月26日に、課徴金の延滞金の割合の引き下げ(同69条2項)および犯則調査手続における電磁的記録の証拠収集手続の整備(同102条、103条の2~114条の3、116条)は2020年1月1日にそれぞれ施行済みであった。[↩]
- もっとも、少なくとも筆者の経験上は、これはあくまで優先順位の話であって、日本が諸外国に比して制裁が緩いがゆえに日本での対応や独禁法コンプライアンスを軽んじるといったことはないように思う。[↩]
- より柔軟な適用を志向した裁量的な課徴金制度の議論もあり世間を賑わせたが、結果的に導入は見送られた。[↩]
- 立入検査等の強制調査の処分日、犯則調査の臨検等の処分日、または(それらの処分が行われない場合は)違反行為の事前通知日を指す。[↩]
- 実際、平成21年度以降の措置事件では違反行為期間は平均4年となっており、5年を超える事件も多くみられた。筆者の経験でも、違反行為期間が10年近くに上る件も少なくない。あくまで筆者の感覚であるが、改正前の独禁法のもとでは、公取委は、算定基礎となる3年間についてはかなり詳細な調査や認定を行う一方、それより以前の違反については、そこまでの調査を行わなかったり、あるいは保守的な認定を行うことも多かった印象であるから、実際の違反平均期間は4年よりも長かった可能性もある。[↩]
- 施行日前の違反行為部分についての算定期間は施行日前日から最長3年、施行日前の違反行為部分についての算定期間と施行日後の違反行為部分についての算定期間の合算した期間については、調査開始日から最長10年前の日まで遡ることになる(改正附則6条2項~4項)。[↩]
- なお、施行日時点で違反行為終了後5年は超えているものの7年には達していない場合、排除措置命令および課徴金納付命令はともに課されない(独禁法附則3条、5条)。[↩]
- 談合金については、その金額そのものが課徴金として賦課される。[↩]
- 住友電工株主代表訴訟(大阪地方裁判所、平成26年5月7日付和解成立により終了)。[↩]
- 少なくとも改正前の実務では、公取委は、課徴金の算定期間が最長3年であることを踏まえて、3年を超える違反行為については、違反行為終了時点から遡ること3年前の時点で違反行為が存在したことを立証することで、違反行為の厳密な始期は明らかにしないまま、遅くともその時点以降違反行為が存在したと認定する手法を用いることがあった。[↩]

武井 祐生
弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー弁護士
2006年京都大学法学部卒業、2008年京都大学法科大学院修了。2009年弁護士登録、2010年弁護士法人御堂筋法律事務所入所。2018年弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー。国内の談合・カルテルへの対応(リニエンシー、取消訴訟等)や国際カルテル対応(外国競争当局対応、クラスアクションへの対応等)、企業結合審査への対応、独禁法コンプライアンス体制構築サポート等の独占禁止法・競争法分野に加え、M&A・企業再編、争訟・紛争解決、コンプライアンス・企業不祥事を中心に、企業法務全般を取り扱う。
御堂筋法律事務所プロフィールページはこちらから
