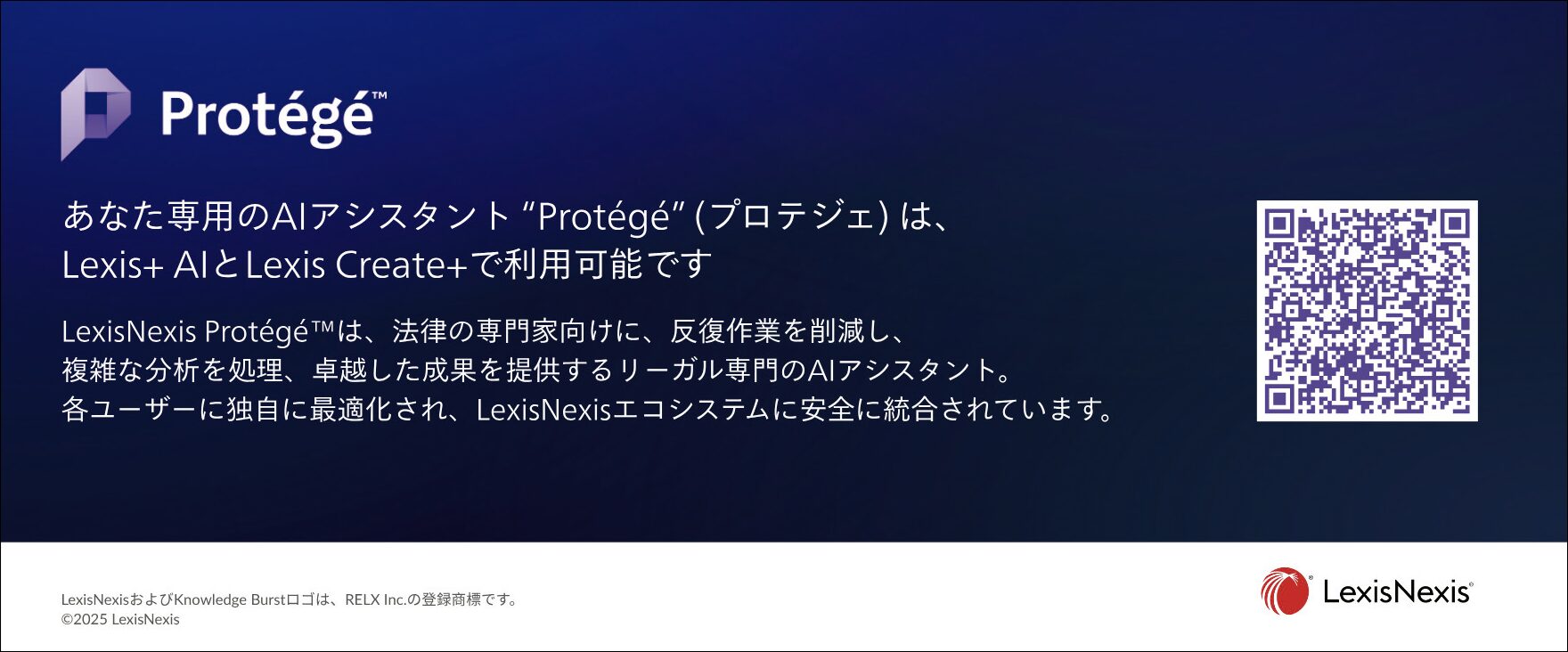生成AIがビジネスの風景を塗り替える中、法務・コンプライアンス分野でもその活用が急速に進んでいる。業務効率化への期待が高まる一方、機密保持や説明責任といった倫理的な課題から、導入に慎重な声も少なくない。
世界と日本では、AI導入の現状にどのような違いがあるのか。そして、法務実務家はリスクとどう向き合い、AIを真の力に変えていけばよいのだろうか。
リーガルテック分野を牽引するレクシスネクシス・ジャパン株式会社のボブ・バビッシュ氏に、AI活用をめぐる世界の最新動向から日本市場独自の展望、そして“責任あるAI”を導入・運用するための具体的な指針まで、幅広く語ってもらった。
世界で進む生成AIの導入と、その背景とは
まず、世界における生成AI導入の現状について伺った。
「私たちレクシスネクシスは、お客様からのフィードバックを大切にするとともに、さまざまな地域の法務実務家を対象に定期的に調査を実施しています。その結果、AIの導入が劇的に加速していることがわかりました」。
2025年初めに、同社のニュースサービス「Law360注1」チームが、米国でAIの利用拡大と法律業界の対応に関する調査「Law360 Pulse」を実施したところ、米国の民間法律事務所の弁護士の50%以上が現在、何らかの目的で生成AIを業務に使用しており、前年の3分の1未満という結果から大幅に増加したという。
「2024年の年末に実施した英国での法律事務所と企業内弁護士を対象とした調査では、弁護士の41%が生成AIを使用しており、さらに41%が使用を計画していることがわかりました。この数字は前年同期比の11%と28%から大幅に上昇しています。
また、企業法務の分野では、米国の非営利団体CLOC(Corporate Legal Operations Consortium)が法務部門を対象とした世界的な調査結果を発表しました。それによると法務部門の30%がAIを使用しており、さらに54%が2年以内にAIを導入する予定であることがわかりました」。
法律事務所では、主な推進要因として、業務をより迅速にこなすこと、クライアントによりよいサービスや新しいサービスを提供すること、そして競争優位性を維持することが挙げられており、一方の企業では、よりよいリーガルアドバイスの提供とビジネスの拡大の支援、加えて、急速に変化する規制環境に対応しながら、限られたリソースの中で、コストと増加する業務量の管理を目指している。
では、日本の現状はどうだろうか。
「日本における私たちの使命は、企業がよりよいガバナンスを通じて持続可能かつ倫理的に成長できるよう支援することです。このため、特にコンプライアンスの分野で企業をどのように支援できるかに強い関心を持っています」。
バビッシュ氏は続ける。
「日本オフィスで実施した最新の調査では、日本企業の法務コンプライアンス部門における生成AIの導入はまだ初期段階にあり、既に使用している、または使用を計画していると回答した企業は55%に留まりました。一方で、現在AIを使用していると回答した企業は約30%で、これはCLOCの調査結果とほぼ一致しています」。
他国と同様、日本企業も業務効率化を追求しており、近年の離職率の上昇や高齢化の進行により、多くの企業では、特に属人化された業務において、人材不足や熟練労働者の不足が深刻な課題となっている。それに対応するためのしくみづくり、組織づくりが優先事項となっているという。
「生成AIの使用に関しては、企業はリーガルリサーチ、要約、ドラフトや回答作成といった分野での活用を期待しています。これは世界的にも共通したニーズであり、当社はこれらのニーズに応えるために「Lexis+AI™」を開発しました。日本の市場における特徴的なニーズは、社内規程やマニュアルを最新の法規制に整合させることです。このニーズに対しては、当社が国内市場で提供するコンプライアンス ソリューション「LexisNexis® ASONE」のエコシステムで対応しており、今後も進化させていく予定です」。

ボブ・バビッシュ 氏
リーガルテック分野の革新をリードするレクシスネクシスの取り組みとは
こうした変化の中、レクシスネクシスではリーガルテックを革新するために、どのように生成AIを活用しているのだろうか。
「私たちは、お客様を支援するためのツールを急速に拡充しており、当社がリードするリーガルテック分野の進展に貢献しています。最近大きな節目となったのは、2025年4月に、国内でも「LexisNexis Protégé™」の販売を開始したことです。これは、エージェント型AIを活用し、よりパーソナライズされた体験を提供する画期的な一歩となりました。Protégéは、エージェント型AIを使用してユーザーの好み、専門分野、法律、文書作成スタイルなどを理解します。レクシスネクシスが誇る信頼性の高いコンテンツに加えてユーザー自身の独自コンテンツを活用することで、パーソナライズされた回答、ドラフト、要約を提供します。さらに文書作成支援や、ユーザーの入力に基づいたワークフローの提案などを通して、ユーザーのリーガル業務におけるAI活用体験を向上させていきます」。
加えて、同社はLexis+AIプラットフォームとMicrosoft Wordに統合されたドラフト作成ツールである「Lexis® Create+」を新たにリリース。Create+は、サンプル文書からドラフトを生成し、レクシスネクシスのコンテンツから根拠を補強することで、ドラフト作成プロセスを効率化する。
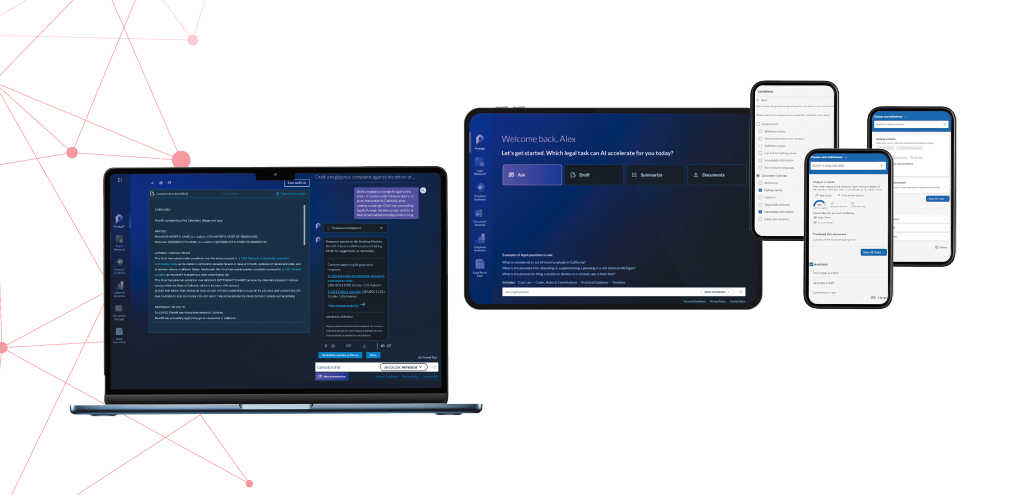
【左】Protégéは、ユーザーの好みや過去の作成例、LexisNexisの豊富なコンテンツに基づき、会話を通じて最適なドラフトを提案します。
【上左】会話型検索、ドラフト作成、法的文書要約、文書アップロード分析—— Lexis+AIが、法務のスピードと精度を一段と高めます。
【上右】Create+ならMicrosoft 365上でパーソナライズされた法的文書のドラフトを簡単に作成できます。
目指すのは“責任あるパートナー”
未来像を尋ねると、バビッシュ氏は次のように語ってくれた。
「私たちレクシスネクシスのビジョンは、すべての法務やビジネスの実務家に、真にパーソナライズされたAIアシスタントを提供することです。既に訴訟法務と取引法務に特化した体験を提供するProtégéをリリースしていますが、今後は、コンプライアンス担当者など、他の分野への展開や、音声インタラクション、規制の将来予測(ホライゾンスキャニング)、マルチメディアコンテンツの処理といった機能の強化を計画しています」。
これらは、“インテリジェントかつ責任ある技術を通じて、法務業務の効率化と意思決定の向上に貢献する”という同社のコミットメントに基づくイノベーションといえる。
「日本でも生成AIの導入は今後さらに進んでいくと考えていますが、その進み方は米国や英国などとはやや異なるものになるでしょう。これは、法制度やビジネス慣習、そしてクライアントのニーズや期待に日本独特のものがあるためです。日本では、AIの導入はより広範なデジタルトランスフォーメーション(DX)の動きと密接に結びついており、多くの企業にとって依然として最優先事項となっています。企業や法務部門が業務のデジタル化を進める中で、社内データと当社レクシスネクシスのコンテンツを統合する新たな機会が生まれています。この融合により、AIによるインサイトや意思決定支援のための強力な基盤が構築されつつあります。
他国の事例を単に模倣するのではなく、日本は独自の優先事項を定義していくことになるでしょう。たとえば、コンプライアンス業務の効率化、高精度のリーガル翻訳、リスク軽減ツールなどが挙げられます。最終的には、AIの活用によって法務業務の効率化にとどまらず、より広範なビジネス課題の解決にも貢献できるようになると期待しています」。
日本および世界における法務実務のAI技術展開と倫理的懸念・規制の影響と企業法務の対応方法とは
一方で、「AI活用にも課題はある」とバビッシュ氏は語る。
「法務実務家の多くは、AIの導入に対して慎重な姿勢をとっています。前述のLaw360 Pulseの調査によると、弁護士の79%がAIの法的倫理に関する理解の不十分さを、技術活用における最大の懸念事項として挙げています。また、半数以上が、クライアントの機密保持、プライバシーリスク、および組織知識の喪失についても懸念を示しています。世界的に見ても、法務実務家の間では、AIツールが単に“機能する”だけでなく、“倫理的で、安全かつ透明性を持って機能する”ことが強く求められています。
日本でも他国同様、法務実務家はクライアントの機密保持、データ保護、およびAIが生成したコンテンツに対する説明責任といった、進化する規則に対応していく必要があります。たとえば、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の「Practice Note SC Gen 23」では、弁護士に対してAIが生成したコンテンツの検証と開示を義務づけており、これは透明性を重視する世界的な動きを反映しています」。
では、これらの課題にどのように向き合っていけばよいのか。
カギとなるのは、“責任あるAIフレームワーク”と“進化する規制”との整合性にあり、法務実務におけるAIツールは、単に性能が高いだけでなく、倫理基準、データプライバシー、規制上の説明責任に適合していることが求められるという。
レクシスネクシスの母体であるRELXは、その責任あるAI原則を通じて以下のような強力なモデルを提示している。
● 人間による監督と説明責任を伴うAIの設計
● バイアスの積極的な排除
● ツールの機能に関する説明可能性の確保
● プライバシーとデータガバナンス要件の尊重
「重要なのは、AIを、法的判断の“代替手段”ではなく、“補完的なツール”として活用することです。企業法務にとってのベストプラクティスは、まず“責任あるフレームワーク”に基づいて設計されたAIツールを選定することから始まります。安全なデータ処理、法務に特化したトレーニング、そしてAIの生成方法の透明性を重視するプロバイダを探してください。社内では、AI活用に関する明確なポリシーを策定し、生成された結果は必ず適格な弁護士がレビューする体制を整えることが重要です。さらに、技術や規制の進化に対応できるよう、チームの継続的な教育や情報共有のしくみを設けることも不可欠です」。
最良の形でAIを活用すれば、法務ワークフローを大きく変革できる可能性がある。ただし、「それは倫理的かつ慎重に導入された場合に限られ、開発の過程がきちんと説明できる製品、法務業務に特化した専用のツールを選ぶことが重要となります」とバビッシュ氏は強調し、インタビューを締めくくった。
→『LAWYERS GUIDE 企業がえらぶ、法務重要課題2025』を 「まとめて読む」
→ 他の事務所を読む
- 「Law360」は、法律専門家、経営者、政府関係者向けに、政策、訴訟の動向、法的トレンドに関する最新ニュースと分析を提供するニュースサービス[↩]

ボブ・バビッシュ
レクシスネクシス・ジャパン株式会社 北アジア・インターナショナル・プロダクトマネージャー
Bob Babish
東京およびニューヨークの大手国際メディア・テクノロジー企業において25年以上の経験を有する。コンテンツや製品戦略を専門とし、ナレッジワーカーの業務効率化と付加価値創出を支援。新市場への製品展開、ローカライゼーション、戦略的パートナーシップ構築に関する深い知見を活かし、アジア全域における事業拡大において重要な役割を果たしている。