はじめに
本連載は、リーガルテック導入やリーガルオペレーションの進化における課題について、法務部長(佐々木さん)と弁護士(久保)が、往復書簡の形式をとって意見交換します。連載第9回は私、久保光太郎が担当します。
問いかけへの検討
―これからの社内弁護士のあり方は?
さて、前回の佐々木さんからの問いかけは以下のとおりでした。
- 今後も、社内弁護士は弁護士資格を持つ人材にとって引き続き魅力のある選択肢となりうるか。
- また、魅力のある選択肢となるために、受け入れ先の企業はどのような努力をしていかなければならないのか。
この問いかけについて、私の考えをお話したいと思います。
社内弁護士数の推移
ここ1~2年ほど、企業の採用担当の方から、「社内弁護士を採用しにくくなった」という話を耳にする機会が増えました。日本組織内弁護士協会(JILA)の調査によれば、企業内弁護士数は過去20年間一貫して増加傾向にありますが、その増加率は低下傾向にあることが見受けられます(図表1参照)注1。その背景にはさまざまな要因があると考えられますが、企業法務分野における法律事務所の採用需要が拡大するなか、社内弁護士の給与水準や仕事の魅力が相対的に低下したことが一つの理由であると思われます。
図表1 企業内弁護士数とその増加率の傾向
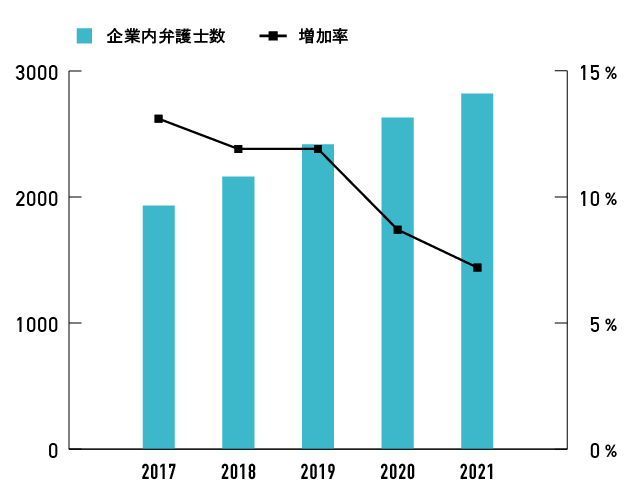
出典:日本組織内弁護士協会(JILA)「企業内弁護士数の推移(2001年~2021年)」を基に作成。
社内弁護士は、激務といわれる大手法律事務所に比べると労働時間が短く、そのポジションが安定している点が魅力といえるでしょう。また、ビジネスの現場との距離の近さも大きな魅力です。外部の法律事務所の弁護士は、特に案件・プロジェクトベースで雇われる場合、自分の仕事の結果を見届けることができません。M&Aを例にとると、多くの場合、外部の法律事務所の仕事は契約のクロージングまでであり、その後の業務(PMIなど)にまで関わることは稀です。他方、社内弁護士はビジネス部門との継続的な関係性のもとで、案件・プロジェクトの全体と将来を見渡して仕事をすることが可能です。
前回の佐々木さんの問いかけにもあった司法試験の合格者数については、ロースクール制度の功罪や弁護士過疎の解消等、複雑な問題が絡み合っているため、ここではその当否に立ち入りませんが、企業法務の世界に限っていうのであれば、その需要(人材ニーズ)は今後も拡大することが見込まれる一方で、現状の枠組みでは、供給(実務家の数)は限られることは間違いありません。したがって、短期的には景気の後退による調整局面はあると思われますが、中長期的には人材の逼迫感は強まる可能性が高いのではないかと思われます。
社内弁護士は魅力のある選択肢?―二つのシナリオを考える
では、そういった背景があるなかで、引き続き社内弁護士は魅力のある選択肢となりうるのでしょうか。
(1) “安定性の高さ”が仇になる可能性も
私は、社内弁護士のポジションの一部がその魅力を失っていくシナリオもありうるのではないかと考えます。1.で述べたように、社内弁護士の仕事は外部の法律事務所に比べると安定性が高い業務といえます。ところが、そうした定型的・日常的な契約審査等の業務は、ともすると刺激が少ないものと感じられ、特に若手弁護士にとっては、「弁護士としての成長につながらない」と敬遠される可能性もあります。
企業としては、“その業務”が採用人数を増やしたり給与水準を上げたりしてでも社内弁護士に担当させる必要があるのかについて、よりシビアな目で見極めることが必要になると考えられます。
(2) ビジネスや経営の一翼を担う魅力
他方で、社内弁護士の仕事の一部は今後ますます魅力的な選択肢となるシナリオも考えられます。こちらも1.で述べましたが、社内弁護士の仕事の最大の魅力は“ビジネスの現場との距離の近さ”にあります。たとえば、多額の資金が集まるスタートアップ企業が既存の規制をディスラプティブに乗り越えていくに際して、そのビジネスの成功のカギを法務が握る…というような事例は、今後ますます増えてくると思われます。そこまで極端な事例でなくとも、大企業において社内弁護士が企業として重要な意思決定の局面に関わっていく事例が増えてくるのではないでしょうか。社の命運を左右するプロジェクトにスペシャリストとして携わるわけですから、企業としては、従来の人事・報酬体系にとらわれない、ポジションに見合った報酬を準備する必要はありますが、社内弁護士にとっても、そうした環境で、自らの知識をビジネスの現場に直接役立たせることができれば、社内弁護士ならではの“やりがい”や“魅力”を感じられるに違いありません。
社内弁護士の未来
以上を要約すると、社内弁護士のポジションは今後、多様化(ないし、二極分化)する可能性があると思います。2.(2)で述べたような業務を担う社内弁護士は業界的にも“花形”となり、仕事のやりがいと多額の報酬が期待されるとして魅力ある選択肢であり続けるでしょう。ただ、一方で、2.(1)で述べたような定型的・日常的な業務については、「社内弁護士が担当すべき業務か」の検討を含め、業務配分の見直しが必要となります。このような未来は、企業と社内弁護士の両者にとって、安定的な「蜜月時代」の終わりといえなくはありません。
もっとも、企業としては、弁護士との関係で、その魅力について過度に悲観したり、魅力を増すために無理して努力をする必要はないと考えます。というのも、以上の事態と同時に、“弁護士”という資格の意味も、今後相対化が進んでいくと考えられるからです。
たとえば、私が現在携わっているクロスボーダー領域の法律問題はさまざまな国・地域の法律が絡み合うため、必ずしも日本法の弁護士資格が重要な意味を果たしません。また、最近ニーズが高まっているDXやデータ分野の業務を見てみると、法律の知識だけではなく、新たなビジネスモデルや、システム、ネットワークに対する理解も必要です。さらに、この連載でも度々話題に出ているリーガルテックのサービス開発に際しても、弁護士資格は本来、必要ありません。
今後の企業法務の世界において必要とされる人材像を思い浮かべた場合、法律の知識や専門家としての物事の考え方を基礎としつつも、自分と異なるバックグラウンドの人々と一緒に仕事ができる幅広い経験や、俯瞰的な視野を持つことが重要になってくると考えます。もちろん一般論としては、資格はあった方が有利なことに違いはないのですが、下手をすると、「弁護士らしい仕事をしなければならない」と意識しすぎる結果、キャリアパスの可能性を狭めてしまう例もあります。
私は、これまで企業法務の現場で、弁護士資格は有しないものの優秀で人柄も素晴らしい企業法務の実務家の方々に数多くお会いしました。社内弁護士が実務に定着した今だからこそ、企業としては、「そのポジションに本当に社内弁護士が必要なのか」を考え直し、組織のあり方を振り返るタイミングにさしかかっているのかもしれません。
 弁護士から法務部長への問いかけ
弁護士から法務部長への問いかけ
法務人材の教育・育成、キャリアパスのあり方とは?
いずれの業界も同じですが、企業法務の未来も、いかに優秀で多様な人材をこの業界に招き入れることができるかにかかっています。次回はこれからの時代の企業法務の人材育成、そしてキャリアパスの在り方について、佐々木さんのご意見をお伺いしてみたいと思います。
そういえば、佐々木さんも最近、キャリアパスの大きな転換(!?)があったことと拝察しております。佐々木さんがどのようなビジョンを持ってキャリア・チェンジを図ったのか、その一端でもご開陳いただければ嬉しいです。
→この連載を「まとめて読む」

久保 光太郎
AsiaWise法律事務所 代表弁護士
AsiaWise Digital Consulting & Advocacy株式会社 代表取締役
AsiaWise Technology株式会社 代表取締役
1999年慶応大学法学部卒。2001年弁護士登録、(現)西村あさひ法律事務所入所。2008年コロンビア大学ロースクール(LL.M.)卒。2012年西村あさひシンガポールオフィス立ち上げを担当。2018年クロスボーダー案件に特化したAsiaWise法律事務所を設立。2021年データを活用するプロフェッショナル・ファームのコンセプトを実現すべく、AsiaWise Digital Consulting & Advocacy株式会社と、その双子の会社としてAsiaWise Technology株式会社を設立。

著 者:佐々木 毅尚[著]
出版社:商事法務
発売日:2021年3月
価 格:2,640円(税込)

