目的とリスクの総合判断 重要論点は知的財産権の帰属確認
事業シナジーを目的とした事業会社によるスタートアップ投資において、重要な確認事項は知的財産権の適切な帰属である。AIや半導体、バイオテクノロジーなど、技術革新が著しい分野への投資が増加する中、知的財産権の瑕疵は投資価値を根底から覆しかねない。
「IPO(Initial Public Offering;新規株式公開)を果たした上場企業であっても、創業時に職務発明規程が整備されていないまま特許を取得しているケースもあります。デューデリジェンス(以下「DD」)で調査すると、発明当時の職務発明規程がなく、知的財産権の帰属が問題になることがあります」。KTS法律事務所の山田健一弁護士はこう語る。
特に注意すべきは業務受託先との関係だ。「業務委託の場合、知的財産権の帰属を定めずに契約を締結すると、業務に関する発明等は基本的に業務受託者に帰属することになります。業務委託契約書で知的財産権が会社に移転する定めを設ける必要があります」(山田弁護士)。
知的財産権が会社に帰属している場合でも、その対価の支払いが適切に行われているかの確認も重要だ。「職務発明により、会社が特許を受ける権利を取得した場合、従業員に対して“相当の利益”を支払わなければなりません。“相当の利益”は会社と従業員との間で協議して、不合理な定めにならないよう設計する必要があります」(山田弁護士)。
DDで知的財産権の帰属に問題がある場合の対応について、山田弁護士は「発明者と会社との間で知的財産権が会社に帰属していることを確認する覚書を締結することが一つの方法です。それも困難な場合は、投資契約書において特別補償条項を設け、真の発明者が現れて損害賠償請求をしてきた場合にその損害を出資先が補償する条項を設けることも考えられます」と説明する。

山田 健一 弁護士
もちろん、投資において求めるスピード感やビジネスの運用上の事情から帰属関係を整理しきれない場合もある。その点はリスクを踏まえたうえでの経営判断が求められると、末吉亙弁護士は指摘する。「最終的には経営判断になりますが、リスク発生の可能性やリスクの大きさは明確にしなければなりません。DDを通じて契約関係を読み解き、我々の経験値を踏まえてそれぞれのリスクをシミュレーションしてコメントします。事業会社側の経験値はまちまちであり、M&Aを頻繁に行う企業の法務部はこうした対応にも精通していますが、そうでない場合や業務量が多い場合は外部弁護士をうまく活用していただきたいですね」(末吉弁護士)。
M&Aに通じる辻川昌徳弁護士も、新規分野への投資時における外部弁護士の有用性を語る。「これまで扱っていなかった事業分野では、業界特有の規制をフォローしきれないリスクがあります。その業界に知見を有する外部弁護士が重点的に確認すべきポイントを絞り込むことで、効率的で確実な検討が可能になります」(辻川弁護士)。

辻川 昌徳 弁護士
投資戦略はWin-Winモデルが基本 リスク管理と成長支援の両立を
辻川弁護士は、投資戦略において自社に有利に交渉を運ぶことにこだわり、投資先のビジネス全体を独占するのは現実的ではないと語る。「実際に“何を独占したいのか”を明確にし、合理的な範囲に限定しないと、契約がブレイクするリスクがあります」(辻川弁護士)。
以前は投資側が有利な条件で契約を持ちかけることが多かったが、コンプライアンス経営とサステナビリティが重視される昨今においては、投資する以上はWin-Winとなる条件が求められるという。公正取引委員会もこの流れを後押しする。
「公正取引委員会・経済産業省の「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(2022年3月31日)において、共同研究契約等の締結の際に独占禁止法上の問題となるケースが記載されています。投資に伴い締結するような共同研究契約でも、知的財産権を事業会社のみに帰属させる契約や、共同研究の大部分をスタートアップが単独で行うことになっているにもかかわらずその成果を事業会社との共有にする契約は、“優越的地位の濫用”として独占禁止法違反となる可能性があります。このようなリスクを踏まえると、必ずしも事業会社に知的財産権を帰属させる必要はありません。競合他社への技術流出防止が目的なら、独占的ライセンスを取得することで、事業会社のビジネス上の利益を確保できます」(山田弁護士)。
「競合他社が既に投資している、または後から投資してくる場合があります。既に競合他社との契約で独占的な権利が付与されていないか、また、自社が投資する段階で将来の競合参入に備えて合理的な範囲で独占的な権利を確保すべきかを検討します」(辻川弁護士)。
近年のベンチャーファイナンスでは、スタートアップの成長を促す公平性を重視した条項が増えているという。スタートアップ投資は、適切なリスク管理と投資先企業の成長支援とのバランスが成功のカギとなる。法務部門には、この両面を見据えた戦略的な助言が求められるが、締め括りとして、末吉弁護士は投資を進めたい経営陣や事業部とリスクの高さに板挟みになるような場合の対応策について「合理的な判断をしたという記録を残すことが肝要です。非常にクリティカルな案件では、外部弁護士から経営層への直接説明も有効です。第三者の専門的見解として説得力を持って伝えられます」と示した。

末吉 亙 弁護士
読者からの質問(投資後の事業シナジーを実現するための投資時の留意点)
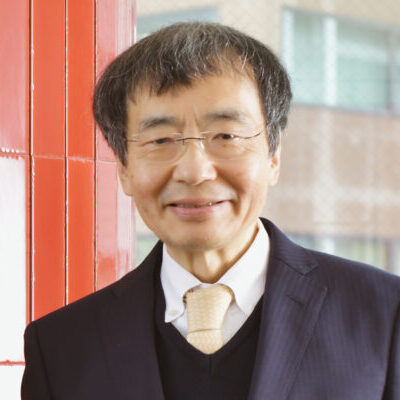
末吉 亙
弁護士
Wataru Sueyoshi
81年東京大学法学部卒業。83年弁護士登録(第二東京弁護士会)、森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所)入所。07年末吉綜合法律事務所(現:潮見坂綜合法律事務所)開設。20年KTS法律事務所開設。

辻川 昌徳
弁護士
Masanori Tsujikawa
04年東京大学法学部卒業。06年弁護士登録(第一東京弁護士会)。12年米国シカゴ大学ロースクール修了(LL.M.)。12~13年Arnold & Porter LLP(ワシントンD.C.・ブリュッセル)勤務。13年ニューヨーク州弁護士登録。23年~KTS法律事務所。

山田 健一
弁護士
Kenichi Yamada
18年立命館大学法学部卒業。20年京都大学法科大学院修了。22年弁護士登録(第一東京弁護士会)、AZX Professionals Group入所。25年~KTS法律事務所。
