―現役知財法務部員が、日々気になっているあれこれ。本音すぎる辛口連載です。
※ 本稿は個人の見解であり、特定の組織における出来事を再現したものではなく、その意見も代表しません。
キミは商標権の“半永久的に存続する”を実感できるか?
『江戸・明治のロゴ図鑑―登録商標で振り返る企業のマーク』(作品社)という本を刊行したのだ。江戸時代、明治時代に大小さまざまな事業者が使ったロゴマークを、当時の登録商標から抽出して紹介するという図鑑である。
日本は、世界的に見ても、創業から100年以上存続するいわゆる“100年企業”の数が、断トツに多い。
江戸・明治時代の商標を眺めてみても、今日も現役で存続している企業の商標がなんと目立つことか。当時から今とほとんど変わらぬデザインの商標を掲げる大企業として、髙島屋やキリンビール、キッコーマンなどが知られるが、中小企業においても、奈良県の藤井利三郎薬房、滋賀県の菊水飴本舗、三重県の赤福など、多くの事業者が、江戸時代からほぼ同じ商標を現代まで伝えている。兵庫県の剣菱酒造など、商標権者は少なくとも4回廃業し、その度に商標に係る権利が転々としているにもかかわらず、商標自体はずっと変わらずに承継され、なんと室町時代から520年もの歴史があるというのだから畏れ入る。
 |
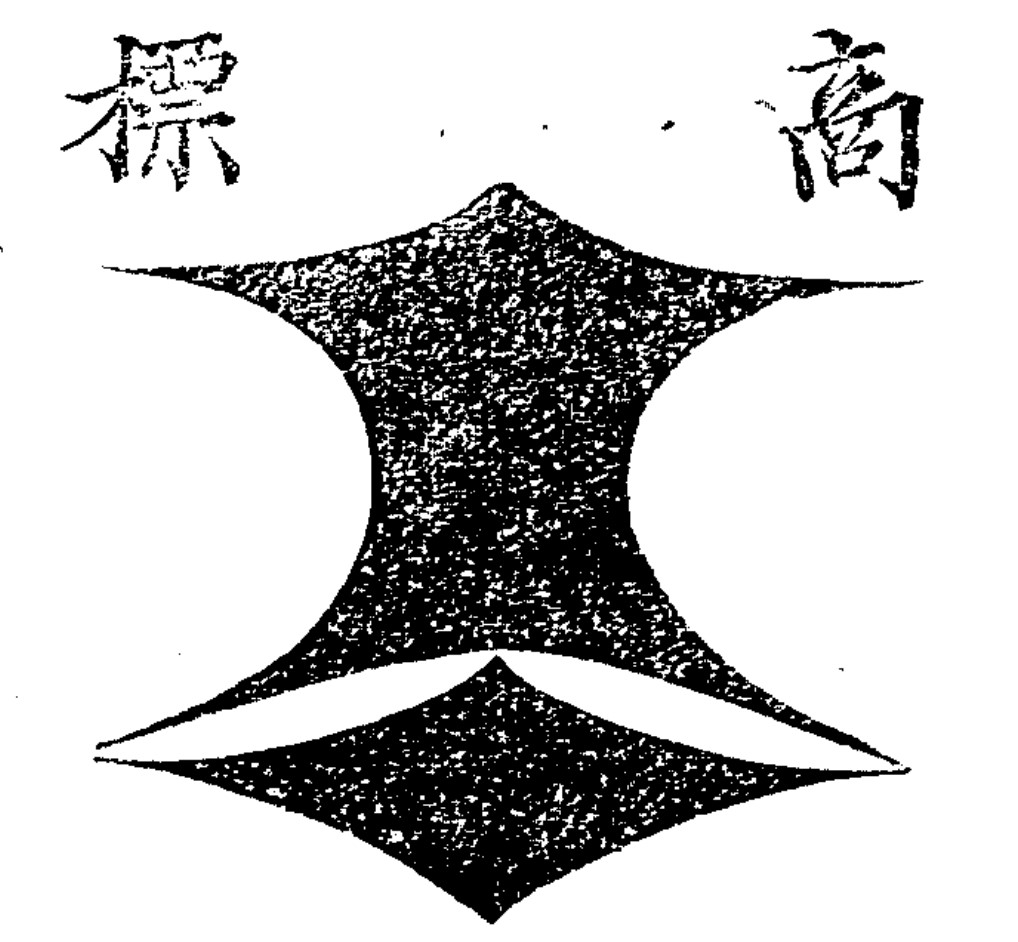 |
| 「髙島屋」の商標(1886年) | 「剣菱」の商標(1885年) |
商標権が、他の知的財産権と決定的に異なる点は、10年おきに訪れる更新登録の手続を行うことにより、“半永久的に権利を存続できること”である。これは教科書的な知識としては、企業の法務・知財実務者にはよく知られていることだ。
しかし、仮に25歳で知財部に配属になって、定年後の65歳までの企業人生をずっと知財業務に捧げたとしても、その間に同じ商標権の存続期間の更新に立ち会えるのは、せいぜい4回までである。実際には異動や転職もあるだろうから、いくら「特許権の存続期間は出願から20年で、対して商標権は永久なのです」と言われたって、一企業人としての主観的な感覚では、どちらも大して変わらない。
歴史を振り返ることでしか、“商標権は半永久的に存続する”を実感することはできないのだ。
「正露丸事件」で争われた“普通名称化した商標の復活”
実感できないといえば、“商標の普通名称化”にまつわるある現象も、容易には実感できない。
“商標の普通名称化”とは、登録商標であったとしても、取引者・需要者において、商標が使用される商品・役務についての普通名称に過ぎないと認識されてしまえば、商標権としての効力を失う現象である。正確には「普通名称と認識される」というより「商標としての認識を失うこと」(識別力の喪失)によって商標権の効力は失われる。
普通名称化自体については、現に普通名称化した商標(「ホッチキス」「エスカレーター」など)や、普通名称として使われることもあるがゆえに、その対策に余念のない商標(「レゴ」「ウォシュレット」など)を見ていれば理解できるが、実感がわかないのは、その逆、つまり、「普通名称化した商標が、再び商標として復活する」という現象だ。
普通名称化した商標の“復活”の是非は、実際に争われたことがある。“商標の普通名称化”をめぐる日本の裁判例で最も有名と言っても過言ではない「正露丸事件」においてだ注1。
本件は、「正露丸」の商標権を有する大幸薬品が、類似商標「イヅミ正露丸」を用いる事業者を、2005年に大阪地裁、大阪高裁において商標権侵害等で訴えたものの、「正露丸」には自他商品識別力がないとされ、敗訴したというものである。
実は、「正露丸」の商標権については、1960年の裁判注2で既にその有効性が争われており、商標登録がなされた1954年の時点で普通名称であったことが認定されている。
にもかかわらず、2005年に大幸薬品が再び商標権を主張したのは、同社が、その後の約50年間にわたる宣伝広告やブランド訴求、営業努力によって、「正露丸」は商標・商品表示として“復活”していると考えたからであった。
普通名称化した商標が復活する条件とは?
だが、結果として裁判所は、「正露丸」の名称で胃腸薬を販売する同業他社が多数併存することなどを理由に、大幸薬品の主張を認めなかった。
このとき大阪高裁は、普通名称が、商品等出所表示(商標)へ転換することを認めるとしたら、以下の条件を満たす必要があると述べている。
例えば,同業他者が消滅し,当該特定の者のみが当該名称を使用して当該商品ないしサービスを提供するような事態が継続し,あるいは,何らかの事情により当該商品ないしサービスが一旦,全く提供されなくなり,一時,人々の脳裏から当該名称が消え去った後,当該特定の者が当該名称を自己の商品等表示(商標)として当該商品ないしサービスの提供を再開するなどの事態が生じ,当該名称が当該特定の者の商品等表示(商標)と認識されるようになったこと等を要するというべきである。
つまり、「正露丸」を製造販売する同業他社が一旦消滅するか、「正露丸」自体がこの世から消滅し、人々の脳裏から「正露丸」という言葉が消え去った後、再び特定人が「正露丸」について自己の商標としての使用を開始し、それが特定の商標だと認識されることが必要だというのである。
しかし、果たしてそんなことが現実に起こりうるだろうか?
理論的にはありうるだろうが、現実的なハードルとしてはとてつもなく高いと思われる。こんな説示をされて、大幸薬品の担当者も途方に暮れたことだろう。現に、同社の50年間の営業努力も奏功しなかったわけだし。
先人から学ぼう! 普通名称化した商標は復活できる!
ところが、江戸・明治時代にまでさかのぼれば、この現象は実際に起こることがわかる。
医薬品、清酒、調味料、化粧品など、古来ある日本の伝統産業で使われた商標には、今日の一般消費者の感覚では“造語”に思われるが、当時において普通名称、慣用名称として商標登録が認められなかった名称が数多く存在する。
たとえば、婦人薬についての「実母散」、小児薬についての「救命丸」「奇應丸」、胃薬についての「胃散」「百草丸」、膏薬についての「無二膏」「相撲膏」、清酒についての「正宗」「男山」などである。
どれも、おそらく通常の読者にとっては、にわかに普通名称とは理解できないだろう。
これらの中には、「正露丸」同様、今日も複数の事業者が併存して使用しており、取引者において自他識別機能を発揮していないと評価できる商標もある(たとえば「実母散」について、キタニの「喜谷実母散」、天恵堂製薬の「天恵実母散」、福岡薬工社の「かめや実母散」などが併存するし、「男山」を含む日本酒も、男山株式会社のほか、小西酒造、八戸酒造、盛田などの多くの事業者が取り扱う)。
だが、まさしく「正露丸事件」で大阪高裁が判示したように、当該名称を用いる事業者が消滅し、その名称が人々の脳裏から消え去った後で、商標として復活を遂げた名称も存在するのだ。
その一つが、江戸時代から使われていた「小町紅」。紅筆で塗るタイプの日本式の口紅について使われた名称だ。
この名称は、1884年に商標制度ができるまでに普通名称化していたようである。一度、ある事業者によって商標登録されるも、同業者組合からの請求により、1887年に無効とされている。
しかし、大正時代以降、洋風のスティックタイプの口紅が広まると、日本式の口紅自体が廃れていく。この過程で、普通名称としての「小町紅」も人々の脳裏から消え去ったのだ。
そして現在、「小町紅」は化粧品メーカーの伊勢半本店の登録商標である。2004年と2021年に登録され、今や珍しい日本式の口紅に使用されている。
「小町紅」という名称で口紅を販売する事業者が他に見当たらないこと、「小町紅」を普通名称として認識する者は今やほとんどいないであろうことを踏まえると、伊勢半本店の商標権は有効と考えられる。
かつて普通名称と認定された「小町紅」は、117年の年月を経て、商標として復活を遂げたのだ。普通名称化した商標の復活は、100年単位で観察すれば、絵空事ではないのである。
つまり、2122年くらいまでがんばれば、「正露丸」も商標として復活できるかもしれないということだ。
2122年。22世紀だ。ドラえもんの誕生が2112年だから、それよりも後である。
これを聞いて、「とっくに定年退職どころか死んでるよ! やる気出んわ!」と思うか、「地道に商標としての訴求を続けていけば、何代か先の知財担当者にとって大きな成果になる。
その時のためにがんばろう!」と思うか。
皆さんはどちらだろうか。筆者は前者…ウソウソ、もちろん後者である。
→この連載を「まとめて読む」
参考:伊勢半本店『紅ミュージアム通信』Vol. 44(伊勢半本店本紅事業部)

友利 昴
作家・企業知財法務実務家
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業で法務・知財実務に長く携わる傍ら、著述・講演活動を行う。最新刊に『江戸・明治のロゴ図鑑―登録商標で振り返る企業のマーク』(作品社)。他の著書に『エセ商標権事件簿』(パブリブ)、『職場の著作権対応100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)、『エセ著作権事件簿』(パブリブ)、『知財部という仕事』(発明推進協会)、『オリンピックVS便乗商法—まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘』(作品社)など。また、多くの企業知財人材の取材・インタビュー記事を担当しており、企業の知財活動に明るい。一級知的財産管理技能士として、2020年に知的財産官管理技能士会表彰奨励賞を受賞。
Amazon.co.jpでの著者紹介ページはこちら。
